今回は【大学4年間のマーケティングが10時間でざっと学べる】を参考に、マーケティングについてまとめてみました。
データ社会になりデータを扱うことの重要性が増し、マーケティングについて学んでおく必要があると考え投稿にいたりました。
前回の投稿では【消費者のプロセス】【マーケティングリサーチ】【マーケティング戦略】の3項目について扱いました。
今回は【製品】【価格設定】【プロモーション】をテーマに扱っていきます。
参考書を読み、重要だな・面白いなと思った箇所を紹介しますのでマーケティングについて全てを網羅することを目的とした投稿ではないのでご容赦ください。
製品開発
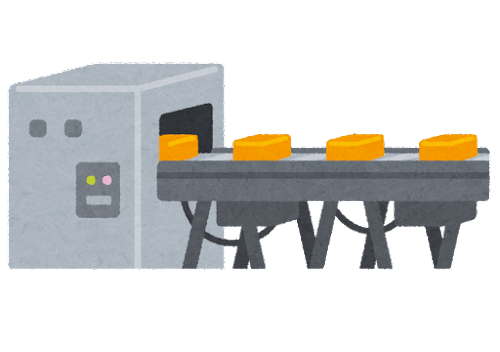
製品開発のプロセスは
- コンセプトの開発
- マーケティング戦略の立案と事業性の分析
- 製品の試作化
- テスト
の順が基本となっています。
製品開発にあたってのアイデア出しで有名な手法はKJ法と呼ばれているものがあります。手順は以下の通りです。
- アイデアの書き出し
- アイデアの分類
- 分類の視覚化
- 図解の叙述、解釈(グループの全体像を文章化)
また製品開発にあたっては顧客のニーズに応えることが必要ではありますが、顧客の声を真摯に聞き過ぎた結果イノベーションのジレンマが起きることもあります。
※イノベーションのジレンマとは、顧客のニーズに応える持続的イノベーションが行われる一方で、新規参入企業が主力企業にとって重要でない顧客のニーズに応える破壊的イノベーション続けた結果市場を一新させ業界リーダーになってしまうことが起こってしまうことをいう。
価格は戦略と整合的に決める

価格設定にあたっては、単に値段を下げれば売れるのものではなく以下のような設定方法があります。
- コスト志向:原価に一定率の利益を上乗せするマークアップ・プライシング
- 競争志向:他社の実勢価格を参考に価格を設定
- 需要志向:留保価格から利益が最大になるように価格設定
価格を変動させることによる売り上げへの影響を表す指標を価格弾力性といい、以下のような式で表される。
価格弾力性=(需要の変化率)÷(価格の変化率)
※出た値の絶対値が大きいほど価格の影響力は大きい
消費者と価格

消費者にとっての価格の意味は以下のようなものがある。
- 支出の痛み
- 品質のバロメーター(製品への知識が乏しい時)
- プレステージ性(高級品へのステータス)
また留保価格(受容できる価格)は人によって違うが、同じ製品を違う価格で販売するのは大変なことであるため以下のような対応がなされる。
- 個別プライシング:価格を個人ごとに変える(車・家電など)
- 商品へのバージョン化:versionを設けて選択させる(松竹梅など)
- セグメント別プライシング:グループ別に価格設定(学割・ランチセットなど)
価格の心理的側面
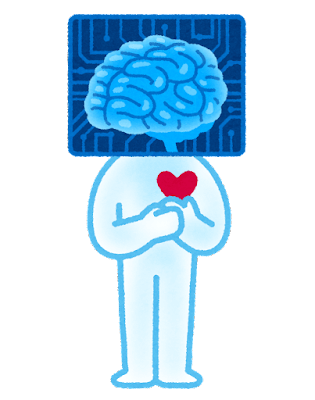
心理学的にみて価格設定の影響は以下のものがあります。
- 参考値からの乖離に基づいて評価
- 複数の利得は分離し、複数の損失は統合した方が価値があがる(プレゼントは小出しにしたほうが良い)
- 「大きな利得と小さな損失」は一緒に、「大きな損失と小さな利得」は分離したほうが価格への価値は高まる(天引きやポイント制度)
プロモーションの種類
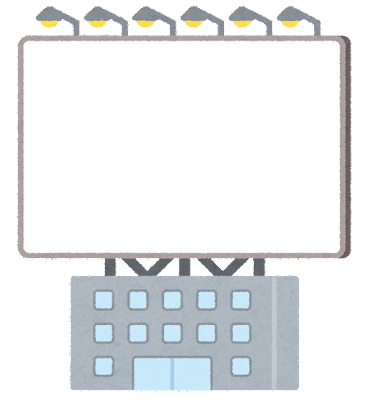
プロモーションには大きく4種類あります。
- 広告
- パブリシティ
- 販売促進
- 人的販売
上2つを認知を促して惹きつけるPull戦略といい、下2つを欲求を高め購買を促すPush戦略といいます。上の方がよい大人数へ関与しますが、下に行くほど効果は高まります。
広告のマネジメントプロセス

広告を出すにあたってのプロセスは以下の通りですが、「目的は何か」が一番重要になってきます。
- 目的の明確化と目標設定
- 予算の決定
- メディア計画
- クリエイティブの作成
- 評価
最初の「目的の明確化と目標設定」にあたっては、大きく以下3つの目的があります。
- 情報提供型(認知・理解促進)
- 説得型(興味・欲求を喚起し、態度形成させる)
- リマインダー型(イメージ構築や記憶を呼び起こす)
また最後の「評価」にあたっては、以下4つの指標(AIDA)が用いられることがあります。
- A:助成認知率/非助成認知率
- I:ブランドのイメージ評価
- D:購入要因・イメージ評価
- A:ブランド選択・売上
広告のメディア

「マーケティング=広告」というほど広告はメジャーな存在です。
予算の決定には以下のような方法があります。
- 支出可能額法:広告を保険と考え可能な限り支払う
- 売上高比率法:売上の一定の割合を支払う
- 競争者対抗法:相対的な支払いシェアに影響を与える
- 目標基準法:数値目標に向けての費用対効果
またメディア計画において、メディア媒体とそのプロセス決定は「リーチ」「フリークエンシー」「GRP」「インパクト」などの指標を用います。
なお広告媒体が複数ある場合はメッセージやイメージなどは統一感が無ければいけない。
インターネット広告

昨今のインターネット広告は日進月歩で進化していて、2004年にラジオ広告/2006年に雑誌広告/2009年に新聞広告/2016年にマス4媒体の広告総額を超すほどになっています。
インターネット広告の特徴としてはタイプによってターゲットのサイズを変えることが可能となり、以下のような手法が用いられます。
- ディスプレイ、バナー広告(同一コピー)
- コンテンツマッチ広告(webページに合わせた広告)
- リスティング広告(検索連動型)
- 行動ターゲティング(cookieを利用)
またSNSやブログなどの口コミによる影響も出てくるため、AIDAにShareの要素を加えてAIDASとも呼ばれます。
今回は以上になります。
扱ったテーマとしては【製品】【価格設定】【プロモーション】の3項目になります。
それではSee you next time!!



コメント