Q:世界の宇宙産業において、これからどのような会社が活躍していくのでしょうか?
皆さん宇宙ビジネスと聞くと「自分とは関係のない業界のことだ」と思ってはいませんか?
実は宇宙ビジネスはロケットの打ち上げだけでなく、カーナビに利用されているナビゲーションシステムやグーグルマップなど私達の生活に非常に貢献していて必要不可欠な業界なのです。
前回の投稿では宇宙ビジネスの全体像を紹介しました。
今回は市場セグメント別にキープレイヤーとなる会社を紹介していきます。
各セグメント内においても複数有力な企業が存在しますが、なかでも特筆すべき企業を筆者の独断でチョイスして解説していきます。
宇宙へのアクセス
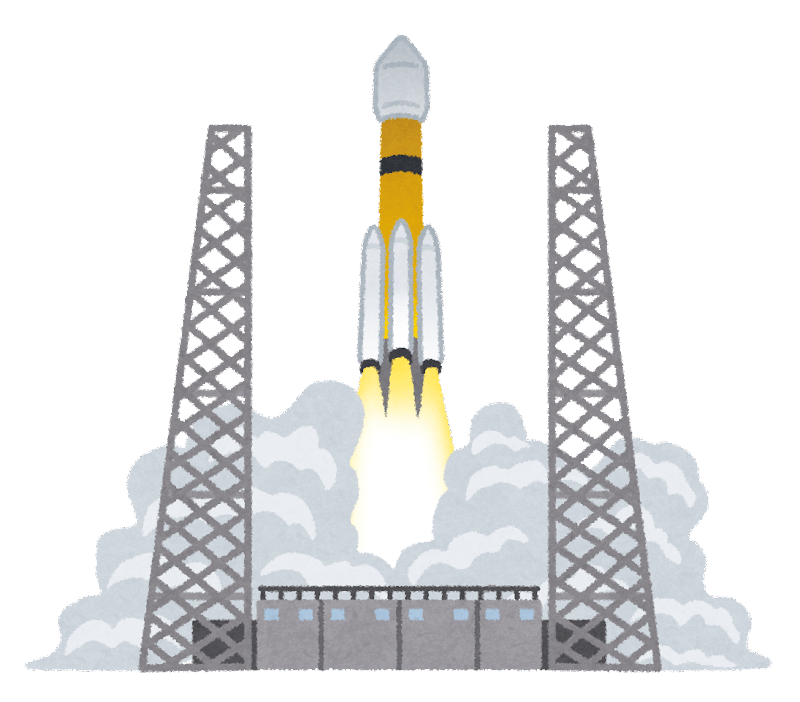
大型ロケット
2005年~2014年の10年間で合計1021回の打ち上げが行われ、そのうちアメリカ301回/ロシア206回/欧州161回/中国131回/日本59回の内訳となっていて日本は世界的にはまだまだ宇宙後進国であることがわかります。
アリアンスペース
現在はエアバスグループの一社になっている欧州の企業。
静止軌道上への通信・放送衛星の投入で市場50%以上のシェアを獲得しており、これまで250機以上の打ち上げに成功しています。
後に紹介する衛星コンステレーションを企画するワンウェブ社から29回の衛星インターネット関連の打ち上げを獲得しており、今後も活躍が期待されています。
スペースX
かの有名なイーロン・マスクが率いる企業。
取り扱う分野は幅広く、主に以下を扱い活躍を増している。
- ISSへの物資輸送サービス
- 商業通信衛星打ち上げ
- 次世代GPS打ち上げ
- 海外衛星打ち上げ
- 第1ロケットの再利用
- 衛星インターネット網の構築計画
ブルーオリジン
Amazon創業者ジェフ・ベゾスが率いる企業。
超大型ロケットの開発の他にもエンジンの再利用/衛星インターネット関連の打ち上げを行い宇宙産業の競争に加わっています。
小型ロケット
これから需要が増していくのは大型ロケットよりも小型ロケットと言われています。
かつて小型衛星を打ち上げる場合、大型ロケットに大型衛星と相乗りをして空きスペースに搭載する/ISSから放出/複数の小型衛星をまとめて大型ロケットで打ち上げることが成されてきましたが、打ち上げタイミングが調整しづらく、投入軌道もバラバラになってしまう問題があったため小型衛星専用の打ち上げが求められるようになってきます。
ロケットラボ
ニュージーランドに拠点を持つ米国企業。
150kgの衛星を高度500kmに打ち上げる「エレクトロン」を開発中であり、エンジン製造に3Dプリンターを使用するため24時間毎にエンジンの量産が可能となっている。将来的には毎週のロケット打ち上げを目指しています。
また世界初の民間打ち上げ場を2016年にNZに建設し打ち上げ革命を起こしかけています。
企業価値は$10億以上ともいわれていて、2021年8月25日NYSEに上場しました。
ヴァージン・オービット
2017年にヴァージン・ギャラクティックから分社した企業。
空中発射ロケットの「ランチャーワン」の開発を進めています。
ワンウェブ社などから打ち上げ契約締結済みで2018年に最初の打ち上げを行いました。
衛星インフラの構築(地上局含む)
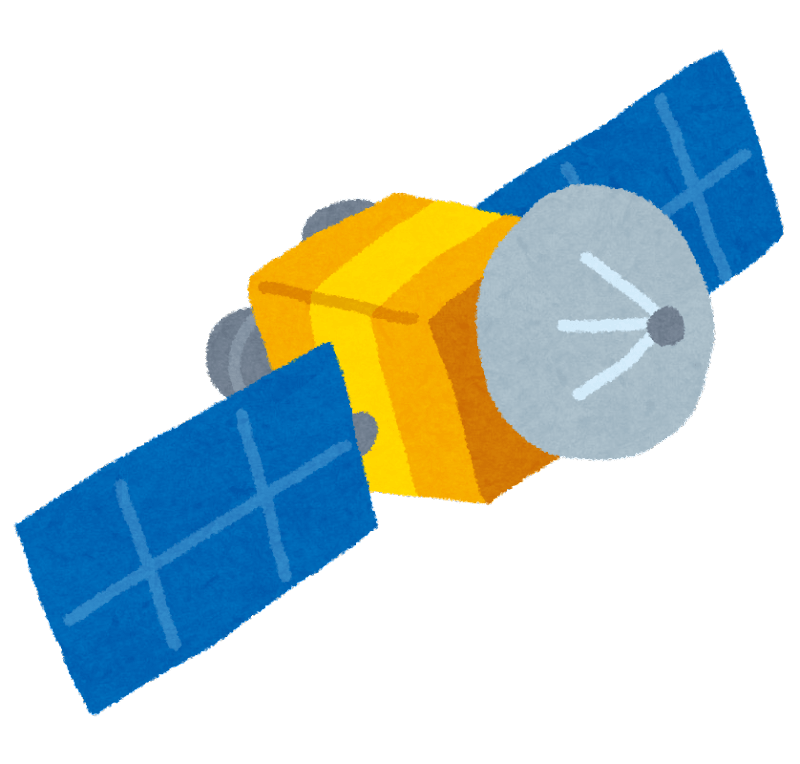
観測衛星
観測衛星はリモートセンシングとして用いられ、光学センサやレーダーなどを搭載しています。気象観測/地図作成/監視などが目的とされていて、気象衛星「ひまわり」は代表的な観測衛星です。
観測衛星紙業は2017年時点で世界市場2,000億円とも言われていて、今後も年率20%で成長が予想されています。
デジタルグローブ
1992年に創業した衛星画像を提供する企業。
2002年には米国政府と長期契約を締結し、衛星画像を提供するようになっています。
画像品質/解像度が圧倒的に優秀で、2014年に打ち上げた分解能31cm「WorldView-3」は世界No.1スペックの衛星です。
米国NGA(国家地理空間情報局)やGoogleマップを提供するベンダが顧客であり、今後も観測衛星市場最大の売上を誇っていきそうです。
プラネット
コンステレーション分野でリードしていてサンフランシスコに本社を構える企業。
コンステレーションとは数百もの小型衛星を地球低軌道に打ち上げ、全体を1つのシステムとして連携させることを言います。コンステレーションのメリットの1つとして1日1回以上の撮影を行うことがあげられます。
同社はアジャイル開発手法を取り入れ衛星の高頻度アップデートを可能にし、随時新規衛星をリプレイスする新たな運営手法を行っています。
また「ブラック・ブリジン社」「テラベラ社」を買収しリモートセンシング分野のトップランナーとなってきました。
通信・放送衛星
新興国での市場成長が期待されています。
通信・放送衛星は静止軌道上にのせる静止衛星と地球低軌道にのせる小型衛星コンステレーションの2種類があり、静止衛星では従来のよりも大容量高速通信が求められてきているためHTSの技術開発中です。
静止衛星のキープレイヤーはエアバスやボーイングなどの古参企業が多い一方で、低軌道衛星通信網を構築するのは以下のような新興企業が多いです。
ワンウェブ
「インターネットに接続できない40億人に安くて高速なインターネットインフラを提供する」をコンセプトに720機の小型衛星を高度1200kmに打ち上げています。
将来的に2620機まで増やす予定で、日本ではソフトバンクGが投資を行っていることで有名です。
スペースX
「スペースXにとって衛星インターネット事業は長期的な収入源と見ており、将来的な人類の火星移住計画の資金源になる」とCEOイーロン・マスクは述べています。
高度1100~1300kmに4425機の衛星を打ち上げる計画を立てています。
ボーイング社
静止衛星だけでなく、地球低軌道にも需要に応じて最大2956機まで小型衛星を増やす予定でいます。
スカパーJSAT
日本の企業ですが最大108機の衛星を打ち上げる予定でいます。
測位衛星
測位衛星に関しては各国政府機関が主導して開発・運用を行っています。
アメリカはGPS/欧州はガリレオ/ロシアはグロナス/中国は北斗/日本は準天頂衛星を運用しています。
地上インフラ
衛星を運用するにあたっては人工衛星本体だけでなく、地上インフラも必要になってきます。
種類としては衛星管制局や地上通信網とインターフェースとなるゲートウェイ局があります。
KSAT
南極含む世界約20か所に地上局を保有するノルウェーの企業。
小型衛星の需要増に伴い小型衛星向けの「KSAT Lite」も増設しています。
日本向けにはスカパーJSATと提携しています。
また地上局の非稼働時間を他社とシェアすることで運用性向上を目指しています。
カイメタ
パラボナアンテナを必要としない平面型受信アンテナを開発したことで有名な企業。
今後はコネクテッドエアクラフト(航空機)/コネクテッドシップ(船)/コネクテッドカー(自動車)への適用が期待されています。
※ここから企業紹介の詳細は省略させていただきます。
衛星及び衛星データ利活用

衛星ビッグデータ
かつて官需がメインだった衛星データ利用も今では民需が活発になってきています。
さらにエンドユーザーに届ける価値がデータ⇒情報⇒インサイト⇒ビジネスアウトカムへと変化してきています。
衛星データをマネタイズするには顧客の業務プロセスとペインポイントを深く理解するために時間を使う必要があります。
参入企業が多いためここでは箇条書きで紹介していきます。
データプラットフォーム構築
- プラネット
- Amazon(AWS)
- IMB
- Microsoft
- オープンクラウドコンソーシア
- シナジーズ(欧州)
画像解析
- オービタル・インサイト(画像解析アルゴリズム)
- デカルト・ラボ(地域紛争解決などが目的)
他データ統合
- クライメート・コーポレーション(農業従事者向けサービス)
- ファーマーズ・エッジ
- ファームログス
- ウェザー・カンパニー(高度な気象予想サービス)
- オービタル・インサイト(金融分野)
衛星インターネット
次世代の低軌道衛星通信網の分野には勢いのある新興企業が多く参加しています。
船舶IoTの分野を開拓しているインテルインサットやワンウェブが有名です。
あえてここで詳しく紹介はしませんが、ホットな分野になること間違いないでしょう。
精密測位と自動化
車のカーナビやポケモンGoにも利用されていますが、自動化の分野での利活用が進んでいます。
日本で1例を出すと農業分野でトラクター等重機を自動で走行させる高精度測位を得意とするマゼランシステムズジャパンがあります。
軌道上サービス

スペースデブリ除去
JS POC(統合宇宙運用センター:デブリ監視)
AGI(デブリ監視)
アストロスケール(デブリ除去衛星の開発)
宇宙ステーション(2024年運用停止)
スペースX(物資輸送サービス)
オービタルATK(補給船)
シェラ・ネバタ(補給船)
ナノラックス(微小重力実験の商業化サービス)
ぺプチドリーム(日本ベンチャー:きぼう内での薬実験)
アクシオム・スペース(商業ステーションの準備)
個人向けサービス
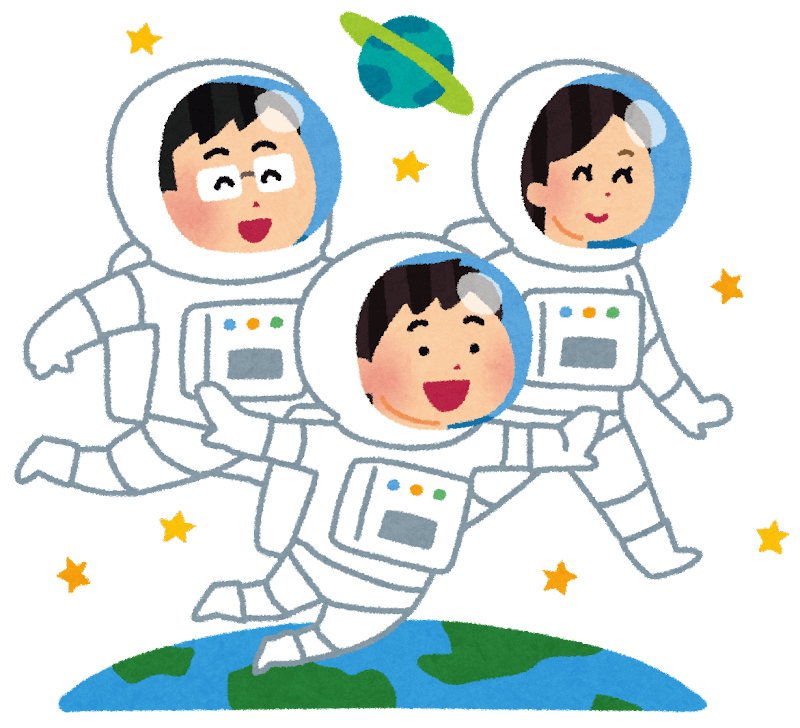
宇宙旅行
ゼロ・グラビティ(弾道宇宙旅行:ディアマンディス氏)
ヴァージン・ギャラクティック(操縦士2人/乗客6人搭乗の有翼宇宙船)
ブルーオリジン(再利用型宇宙船ニューシェパード)
スペース・アドベンチャーズ(ISSへ10泊の宇宙旅行サービス)
スペースX(有人月面周回飛行)
宇宙ホテル
ビゲロー・エアロスペース(膨張式住居モジュール)
深宇宙探査・開発
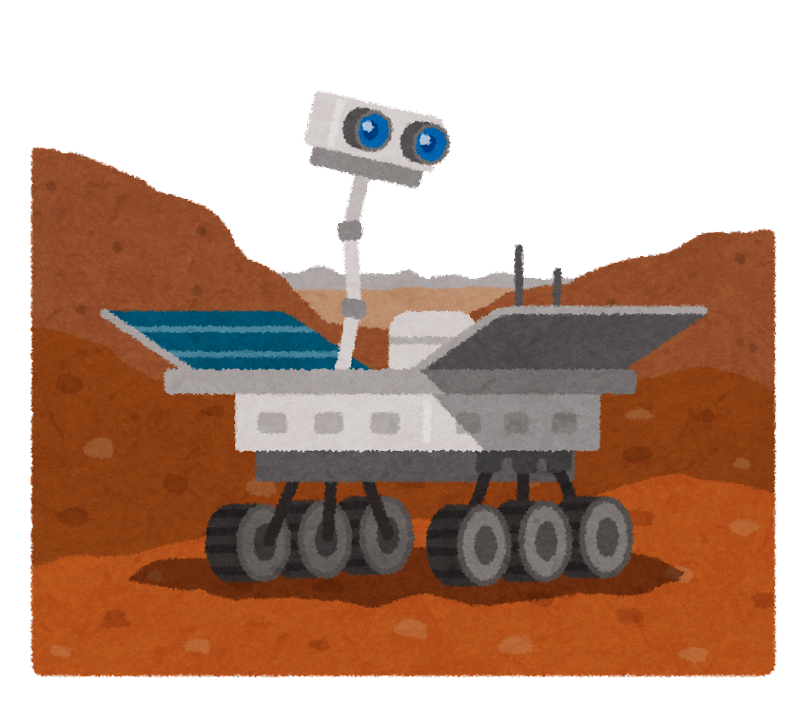
月・火星の探査・開発
NASA(2030年代に火星有人探査)
スペースX(40~100年かけて火星に100万人を送り、自立した文明を築く構想)
ESA(ムーンヴィレッジ:一度に数か月滞在可能な月面基地の建設を構想)
Google・ルナXプライズ
資源開発
ispace(月の資源開発)
以上で宇宙ビジネス【キープレイヤー編】の紹介は終了です。
実は筆者が宇宙関係の業界で働いていて、業界知識の獲得をするとともにもっと多くの人に宇宙ビジネスについて知ってもらいたいと思い今回の投稿にいたっています。
宇宙ビジネスの進歩は目覚ましく、投稿した内容は2017年出版の書籍を参考にしている(以下参照)ので最新の情報を完全に提供できているわけではありませんが、少しでも宇宙ビジネスについて関心を持っていただければ幸いです。
もし宇宙ビジネスに興味も持っていただけたら、↓ぜひ本書を購入してみてください!!
次回は宇宙ビジネスの起業家たちのビジョンについてご紹介していきます。
それではSee you next time!!

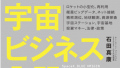

コメント