Q:昨今スペースXなどの宇宙ビジネスが盛り上がっていますが、そもそも宇宙ビジネスが今どのようになっているのか知りたいです。
皆さん宇宙ビジネスと聞くと「自分とは関係のない業界のことだ」と思ってはいませんか?
実は宇宙ビジネスはロケットの打ち上げだけでなく、カーナビに利用されているナビゲーションシステムやグーグルマップなど私達の生活に非常に貢献していて必要不可欠な業界なのです。
今回は宇宙ビジネスへの理解を深めてもらうための初歩として、宇宙ビジネスの全体像を記していこうと思います。
宇宙産業の歴史
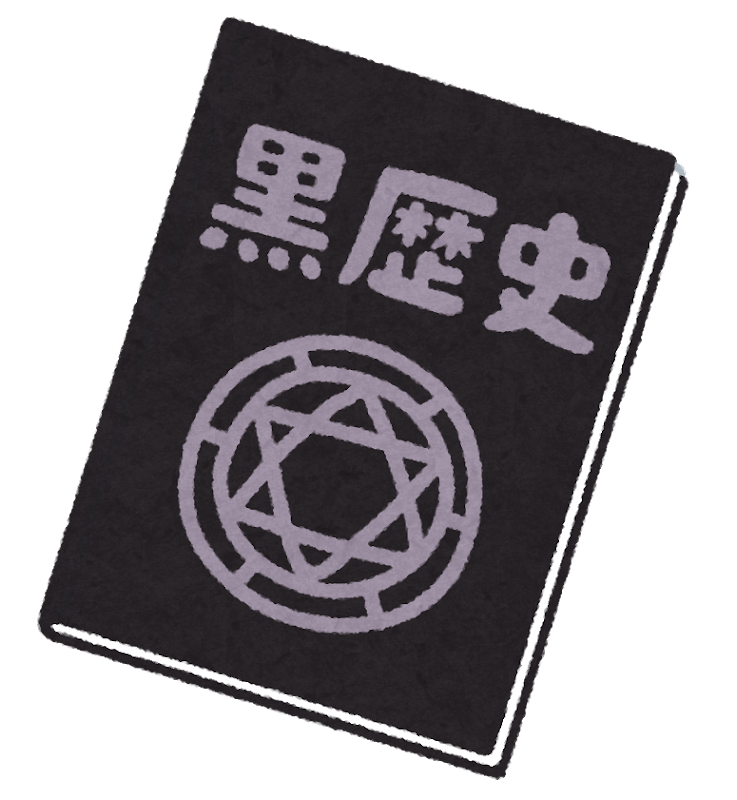
第1ステージ(~1970年代)
第1ステージは国家主導の大型宇宙開発が行われていた1970年代までの時期です。
第二次世界大戦後の冷戦の影響を受け、ソ連とアメリカが互いに競争する形で宇宙産業が発達していきました。
ソ連では1957年に世界初の人工衛星「スプートニク」の打ち上げが成功したことを皮切りに、1961年にはガガーリンが有人宇宙飛行に成功、さらに1965年には初の宇宙遊泳に成功し宇宙業界に大きなインパクトを残しました。
一方アメリカは1985年にNASA(航空宇宙局)が設立され、1961年にケネディ大統領がアポロ計画を発表、1969年には人類初の月面着陸に成功しました。
さらに衛星分野に関しても1972年には地球観測システムであるランドサット計画が立ち上がり、1973年には地球測位システムであるGPS計画が立ち上がり、1978年には初のGPS衛星が打ち上げられました。
第2ステージ
第2ステージは宇宙利用時代と商業化時代となる1980~1990年代の時期です。
主に国が主導してきた宇宙産業を民需側に移していく過渡期でありながら、スペースシャトルやISS(国際宇宙ステーション)の運用が開始された時期でもあります。
また測位・観測・通信衛星の利活用が活発化しました。
GPSの構築が成立し1993年には24機体制がなされました。
欧州では欧州版GPSであるガリレオ計画が1999年に発表され、各地域で独自の測位機能を持つようになっていきました。
巨大企業の再編の裏では起業家ピーター・ディアマンディス氏が民間産業の支援を決意し、Xプライズ財団を設立し、宇宙旅行コンテストを始めました。
第3ステージ
第3ステージは2000年~現代に至る時期で、多くの新潮流が同時多発的に出てきています。
新興企業の勃発もあり、アメリカでは宇宙産業の官民棲み分けを計画し、深宇宙の探査&研究はNASA、地球低軌道体を中心にした商業化は民需で対応するようになりました。
民需の中にはイーロン・マスク率いるスペースX社やジェフ・ベゾス率いるブルーオリジンなどが存在感を強めており、アメリカでは1,000社・欧州では300社以上の新プレイヤーが出現してきています。
Old SpaceとNew Space
従来の宇宙産業をOld Space、これからの新産業のことをNew Spaceと表現し、それぞれの内容を見ていきましょう。
Old Space
衛星の種類
従来活躍していた衛星の種類には大きく分けて3種類あります。
- 通信・放送
⇒2015年時点では衛星1459機のうち5割が通信衛星であり、BS放送/CS放送/飛行機のWi-Fiに利活用されている。 - 測位
⇒GPS/ガリレオ/グロナス/北斗/準天頂などの衛星があり、各地域でナビゲーション等に利活用されている。 - 観測
⇒気象衛星や安全保障衛星が存在する。観測衛星のうち半分は官需となっている。
バリューチェーン
バリューチェーンとして種別すると4種類に分類することができます。
右側に記載されているのはそれぞれの市場規模であり、宇宙産業として有名なロケット事業は実は少額市場なことがわかります。
- 衛星の製造(139億ドル)
- 衛星の打ち上げ(55億ドル)
- 衛星の運用(1134億ドル)
- 関連サービス(1277億ドル)
顧客の種類
宇宙産業は大きく分けて国向けの官需と、市場向けの民需があります。
世界的には官需が25%、民需が75%となっていますがアメリカでは70%が官需となっていてまだまだ国家産業であることがわかります。
アメリカ官需の主な顧客は以下の通りで、日本の宇宙関連国家予算が3,000億円なのに比べると桁違いに規模がでかいのがわかります。
- 国防総省:2.5兆円(安全保障)
- NASA:2兆円(科学技術)
- NOAA(米海洋大気庁)
New Space
新たな宇宙産業を以下5種類の観点から見ていきましょう。
プレイヤー/ビジネスマインド
キープレイヤーなどは次回の投稿で具体的に紹介しますが、スペースX社イーロン・マスクは「人類を火星に送り込む」と言い、ブルーオリジン社ジェフ・ベゾスは「数百万人が宇宙に暮らし、働く世界を作りたい」と言いそれぞれ宇宙産業を盛り立てています。
また伝統的な企業であるエアバス社もワンウェブ社と連携して、新たな宇宙産業を盛り立てています。
法整備/政策
欧州では2000年過ぎに商業宇宙活動法の制定を行われ、日本では2016年に宇宙活動法の制定が行われました。
テクノロジー
放射線/熱真空/振動などの環境試験のknow-howを持つ伝統的宇宙開発技術と、チープテクノロジー/プロセッシング能力/アジャイル開発/3DプリンタなどのIT業界の新技術が融合した結果、とてつもないビッグ産業が誕生しようとしています。
リスクマネー
New Spaceの資金は以下のような人・組織から流れてきています。
- ビリオネアの自己投資
- エンジェル投資家の資金提供
- ベンチャーキャピタルの投資
- 政府からの補助金(シーズ投資/技術開発投資/サービス購入)
産業プラットフォーム
宇宙産業にいる人達の交流会や、宇宙産業に特化したプロフェッショナルメディアがアメリカには存在しています。一方日本では宇宙ビジネスを人材・メディアの観点から支える基盤がまだ整っていない現状にあります。
宇宙産業のセグメント
宇宙ビジネスにはどのようなジャンルがあるのかを見ていきましょう。
宇宙へのアクセス
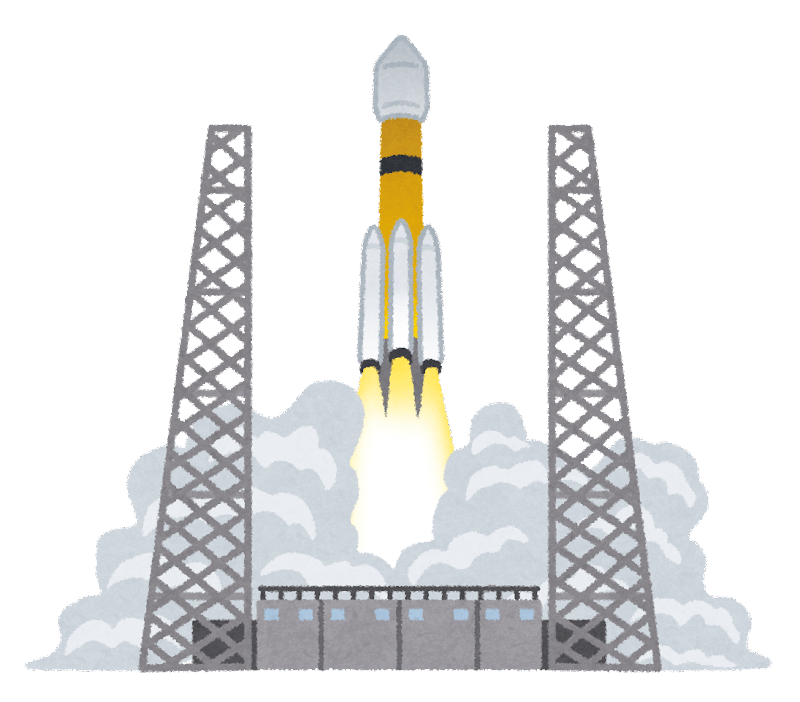
いわゆるロケットで宇宙へ衛星等ペイロードを届ける産業です。
大型ロケットには大型衛星を小型ロケットには小型衛星を搭載します。
なお今まで小型衛星は大型ロケットの大型衛星の余白分に搭載されることが多かったですが、投入タイミングがなかなかないことなどが問題になり、最近では小型ロケットの利用が増えています。
衛星インフラの構築(地上局含む)
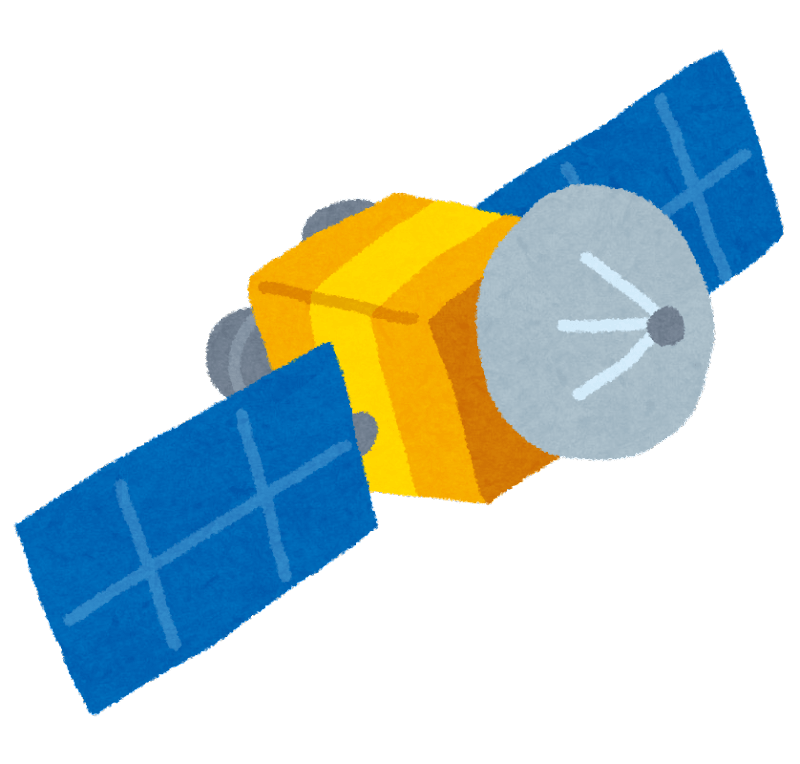
衛星の製造を行っている産業です。
静止衛星(高度3万6000km)/低軌道衛星(高度数100~2000km)/極軌道衛星など投入軌道によって衛星は異なります。
また高機能化が求められる大型衛星/コンステレーションを組む小型衛星などによってもジャンル分けされます。
衛星及び衛星データ利活用

人工衛星から得られる知見/サービスを利用する産業です。
従来は通信・放送、測位を活用したナビゲーションが主として利用されていましたが近年はイネーブラーとしての宇宙技術(何かを可能にする)がキーワードとなり、観測衛星のデータと地上のデータを統合して各産業にソリューションを届ける分野(ジオ・インテリジェンス分野)や通信衛星を活用した分野(ユビキタス・コネクティブ分野)にも利活用の幅が広がってきています。
軌道上サービス

文字通り人工衛星を投入する軌道上における産業です。
軌道上に多数存在する宇宙ゴミ(スペースデブリ)を除去するデブリ除去サービスや、高度400kmに存在するISS(国際宇宙ステーション)もその一例です。
個人向けサービス
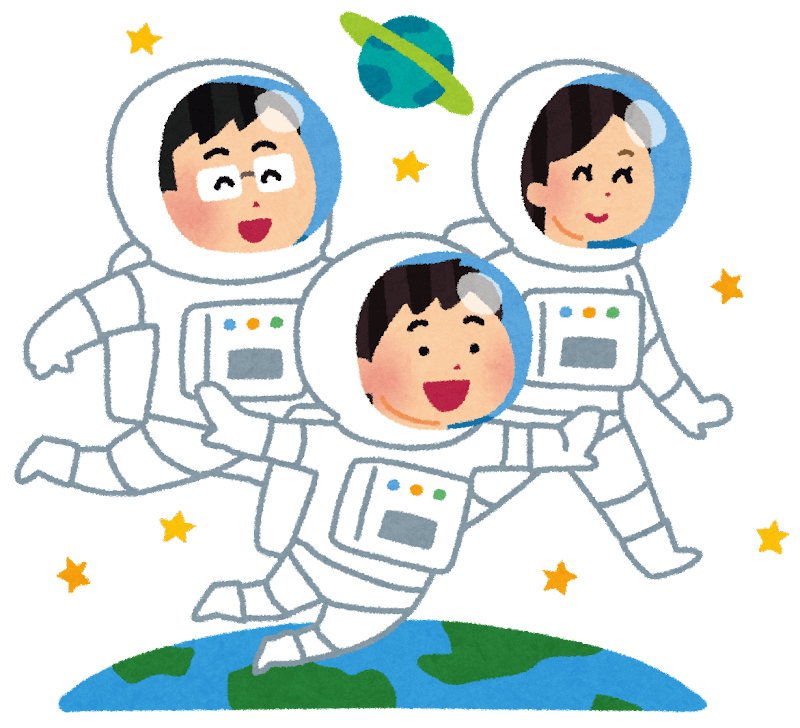
個人向けのサービスとしては宇宙旅行サービスが今のところ有力です。
主に以下のような種類が企画されています。
- 弾道宇宙旅行
- ISSへの滞在
- 月周回軌道旅行
- 宇宙ホテル滞在
深宇宙探査・開発
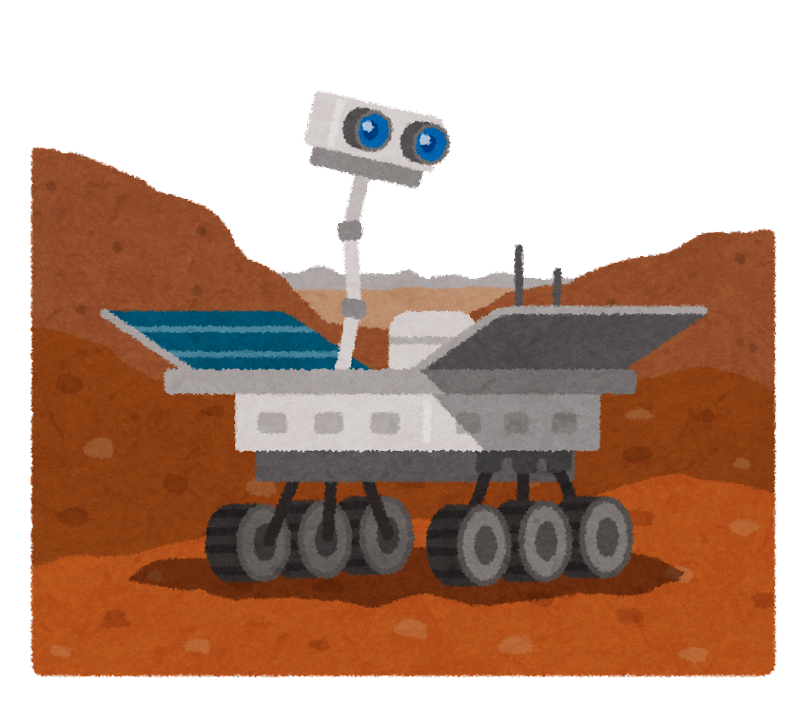
NASAがメイン業務とするより遠くの宇宙を開拓する産業です。
地球環境問題やエネルギー問題が取り沙汰されるようになってきており、水/金属資源/レアアースなどの宇宙資源の開発や地球外での存続を模索する動きが出てきています。
以上で宇宙ビジネス【概要編】は終了です。
実は筆者が宇宙関係の業界で働いていて、業界知識の獲得をするとともにもっと多くの人に宇宙ビジネスについて知ってもらいたいと思い今回の投稿にいたっています。
宇宙ビジネスの進歩は目覚ましく、投稿した内容は2017年出版の書籍を参考にしている(以下参照)ので最新の情報を完全に提供できているわけではありませんが、少しでも宇宙ビジネスについて関心を持っていただければ幸いです。
次回は宇宙ビジネスの市場セグメントとキープレイヤーについて紹介していきます。
こうご期待ください!
それではSee you next time!!



コメント