Q:私達の行動に影響を与えている大きな力はいったい何なんでしょうか?
私達は日々、何かしらに影響を受けて生活をしています。
日常で目にする広告やTV、人の会話など影響を与えるものは多数存在します。
今回は世界的名著である「影響力の武器」を参考に、その正体を一緒に考えていきましょう。
本書はあのメンタリストDaiGoさんが心理学を学ぶきっかけになったという一冊です。
心理学を学びたい人、影響力の武器から自分の身を守っていきたい人などはぜひ本書を購入して読んでみてください。
今回は本書の第2章「返報性―昔からあるギブ・アンド・テイクだが・・・―」を参考に、私の心の琴線に触れた箇所を中心に考察していきたいと思います。
具体的に以下のような疑問・問題を抱える人にはぜひ読んでみていただきたいです。
Q:人から受けた恩は何だか返さなくてはいけないように感じてしまいます。このような気持ちはなぜ生じるのでしょうか?
Q:買いたくもないような商品で、販売担当者と少し揉めたけど、購入後はなんだかその商品の愛着が湧います。なぜなんでしょうか?
Q:営業をしています。どうしたらもっと交渉上手になれるでしょうか?
返報性のルールはどのように働くか

これは「他人がこちらに何らかの恩恵を施したら、自分は似たような形でそのお返しをしなくてはならない」というルールです。
P.35
返報性って言葉は聞いたことがありましたが、実際に心理学として取り扱われていることは初めて知りました。確かに誰かに良いことをされたら、どっかしらでお返しをしたくなってしまうのは確かです。
また「やられたらやり返す。倍返しだ!」なんて某TV番組の名ゼリフがあるだけに、悪意に対しても適用される法則なのかもしれません。
お返しをしたいという気持ちは、大きな文化の違い、遠く隔たった距離、急迫した飢餓、そして長い年月や目先の自己利益を超越していたのです。
P.38
相手が外国人であろうが、価値観が異なろうが、貧乏人であろうと金持ちであろうと関係なくこの法則は適用されるみたいです。
間違いなく、人間社会は返報性のルールから非常に大きな利益を得ています。そこで、人間社会はその成員がこのルールを厳守し、信じるように教育しようとします。
P.41
返報性のルールがもし人間に備わっていなかったら、どうなるでしょうか?
どうせ良いことをしても、返ってこないんだったらそもそも良いことをしようとする人はいなくなってしまうのではないでしょうか?大なり小なり何かしらの見返りがあると期待して私達は相手に何かを与えたりしているはずです。
「情けは人の為ならず」ということわざにもある通り、人に対して行う行為は最終的には自分のためである、というのは周知の事実です。こういった相互関係性を持っているからこそ人間は社会を形成し、発展できてきたのでしょう。
頼み事をしてくる相手への好感度という、普通ならとても大きな要因の影響をいとも簡単にしのいでしまうところに、返報性のルールの強さが見て取れます。
P.44
たとえ相手が嫌いな人であっても、良いことをされたら良いことをしてあげたくなってしまうということですが、人間の好き嫌いという感情をも上回る力は偉大です。もちろん好きな人からされる善行と嫌いな人からされる善行では意味合いが異なってはきますが、どうもやられたらやり返すのが人間らしいです。
相手が施しを求める前に施しをしておくというこの戦略は恐ろしいほど成功しました。
P.46
最近はあまり見かけなくなりましたが、駅前で募金活動を行っている団体はよくいます。そうした人達の中には赤い羽根を募金してくれた人に着けてあげる慣例があったりしました。そんな人たちがもし、無理にでも赤い羽根を私達に無料で着けてきたらどうでしょうか?募金をしたことになるトレードマークを先に着けてくれたのだから、あとは少額募金せざるを得ない状況になってしまうのではないでしょうか?なおさら、その募金団体が子どもたちの集団であったらなおさらですよね。
無料試供品を配布する販売促進員は、相手の力を利用して敵を倒し柔道家と同じです。製品の存在を知ってもらいたいだけというような振りをしつつ、贈り物につきものの報恩の義務の力を起動させているのです。
P.52
タダほど怖いものはない、なんて言われたものですが、つまるところ勝手に恩を押し付けられたら何かしら良い評判を言ったり、再度購入してしまうように私達は法則づけられています。だからこそ、タダには気を付けなければいけませんね。
返報性のルールは、お金も商取引も関わらない、人と人との関係のみが存在する多くの場面も支配しています。
P.54
マッサージなどのサービスに対して適当な対価を支払うのは、金額という数字に可視化されているのでわかりやすいですが、それ以外の人間関係においても返報性は適用されるみたいです。
例えば言葉でもそうです。落とし物を拾ってくれたら、「ありがとう」と言って感謝を示し、事故を起こしてしまったら被害者に「ごめんなさい」と言って謝罪の意を示します。その言葉は行為に対する気持ちとしての対価を支払っているようにも思えます。
「一度でも彼からそんな恩恵を受けたら、言うことを聞かなくてはいけなくなるとわかっていました。だから、彼には借りを作りたくなかったんです。」
P.56
私が大学生の時、後輩にラーメンをおごってあげようとしたことがありました。その時後輩は「親に人からお金に関する恩はもらっちゃだめと言われた」という理由で自分のお金でラーメンを食べていました。ちょっと特殊な例ですが、誰かからの恩恵はきっといつか返さなくていかないように感じてしまうからこその親からのアドバイスだったのかもしれません。先輩後輩などの上下関係においてはいつか、お金以外の形で返せばよかったりするのになーと当時のことを振り返っています。よっぽどお金に困ってたのでしょうか、、、?
様々な組織が、相手が望まないものでも贈り物を与えさえすれば恩義の感情を引き起こせることに気がついています。
P.58
個人間における返報性はまだしも、企業などの営利団体がこの法則を利用してきたら少しやっかいだなと思いました。純粋な温情、ではなく最終的な団体の利益のために恩を売ってきているのだとしたらやっぱり嫌な気持ちになりますよね。
恩返しの義務感は最初に手助けを受けた人だけが感じるわけではありません。その人が属する集団の構成員も同様に感じるものなのです。
P.61
猫の恩返しというジブリ作品があります。個人的に好きな作品ですが、あれも返報性の法則が適用されています。通学中に猫を助けたという理由で、猫の国?に招待されて国から恩返しをしてもらう、という話だったと思います。ある団体のキーパーソン又はその周囲のものに対して善行を行うと、なおのこと大きな見返りがもらえるのかもしれません。
私たちの多くにとって、恩義を受けたままにしている状態というのはとても不快なものです。
P.62
この一文はとても共感できるなーと思ってます。特に恩義をしてくれた人がどのような人かよくわからない状態ではなおさらです。その恩義が何かしら悪意に満ちたもので、あとから請求をしてくる可能性だってないわけではありません。だからこそ、よく知らない人からの恩義は注意が必要です。
人間社会のシステムのなかでは、相互扶助が極めて重要ですから、私たちは恩義を受けたままでいると不快になるように条件づけられているのです。
P.62
返報性のルールを破る人、すなわち他者の親切を受けるばかりで、それに対してお返しをしようとしない人は、社会集団のメンバーから嫌われます。
P.63
興味深いことに、異文化間比較の研究では、返報性のルールを反対の方向に破る人(こちらから与えるだけで、その受け手がお返しをする機会を認めない人)も嫌われる傾向があることが明らかにされている。
P.63
返報性という原則があるからこそ人間社会が成り立っている以上、この原則から逸脱する人は人間社会の発展にとっては悪、つまり排除されるようになっているのですね。人間を作った神様がこのルールをデフォルトで付けたのか?それとも人間が独自に学習していく過程でこのルールを人類共通のものとして植え付けるようになったのか?どっちが正解なのかわかりません。とても興味深く、面白い現象です。
譲り合い

少年が大きな要求から小さな要求に引き下げたのに応じて、本当はどちらにも興味がなかったのに、私は拒否から承諾へと行動を変化させたのです。P.66
拒否させた後に譲歩する
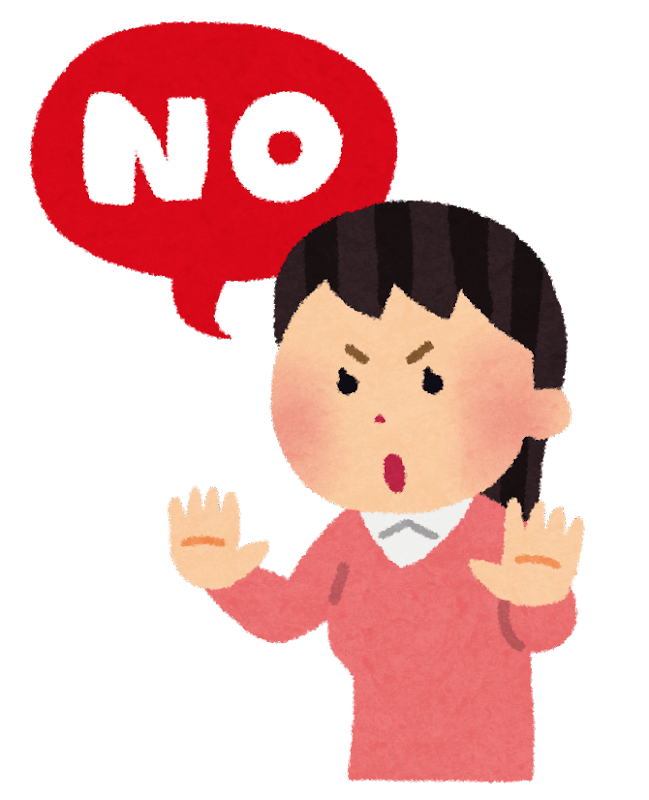
このように見事な効果を上げているので、「拒否したら譲歩」法は自分の要求を通そうという人が意図的に使うことが考えられますし、実際に使われているのです。
P.69
ある提案を行って、それが通らなければ一歩相手に譲った案を再提案するという作戦はどうやらうまくいきやすいそうです。「相手が譲ってくれたのだから、こちらもどっかで妥協しなくてはならないな」と思ってしまう心理というところでしょうか。
最初の要求が法外に大きいと、かえって逆効果を招いてしまうことが示されています。そうした場では、最初に法外な要求を出す人間は、誠実な交渉相手とは見られません。
P.72
あからさまで異常な提案を最初にしてくるのはさすがに自滅でしょう。「なんだこの人は。常識というものを知らないのか?こんな人が言うことは信じられないしなんか怪しい」と思って商談不成立になるのでしょう。
本当に交渉上手な人というのは、お互いが譲歩し、対案を出し合うのに必要なだけ自分の最初の立場を誇張しておき、それによって交渉相手から最終的に自分が望む回答を引き出すのです。
P.72
ここで大切なのは最初の立場を誇張することです。金額などの目に見える提案内容について以上に自分はどのような考え・価値観・力を持っているのかをまずは見せつけた上で、「そんな凄い人が譲歩したのだから、私のような弱い立場の人間も譲歩しなくてはならないな」という気持ちにさせることで交渉成立させているのではないでしょうか?
返報性のルールと知覚のコントラストの原理が組み合わされて使うと、恐ろしいほど強力な力が生み出されます。
P.74
知覚のコントラストとは1番目と2番目に提示されるものが異なっている場合、2番目に提示されるものが実際以上に最初のものと異なっているように考えてしまう傾向のことを言いますが、商談などでは確かにこれは良いコンビになりそうです。
このように心理学的な法則を組み合わせることでより強力な影響力を与えることができるようになるので、もっと心理学のことを学びたくなってしまいます。
奇妙な話ですが、「拒否したら譲歩」法を使うと、相手はこちらの要求を飲むばかりか、実際にそれを実行し、さらなる要求にも嫌がらずに応じようと考えるのです。
P.81
じつは譲歩には、あまり知られていない二つの副産物があります。取り決めに対する、より大きな責任感と、より強い満足感です。
P.81
なぜ、丸め込まれた相手が取り決めの内容を実行するのか。契約条件の作成に関与した場合、人はその契約をより遂行しようとするものだからです。
P.82
自分の値段交渉がうまくいったおかげで、いい買い物ができたと思う人は、買い物への満足感があがり、その製品をまた購入する可能性も高くなるのです。
P.83
結果だけでなく、プロセスを共有することで相手も味方につけてしまうということになります。
商談もやはり人と人とのコミュニケーションによって成り立つものであり、何か一つの共同作業を行うことはその契約周辺のものに愛着として契約後の残っていくのでしょう。
防衛法
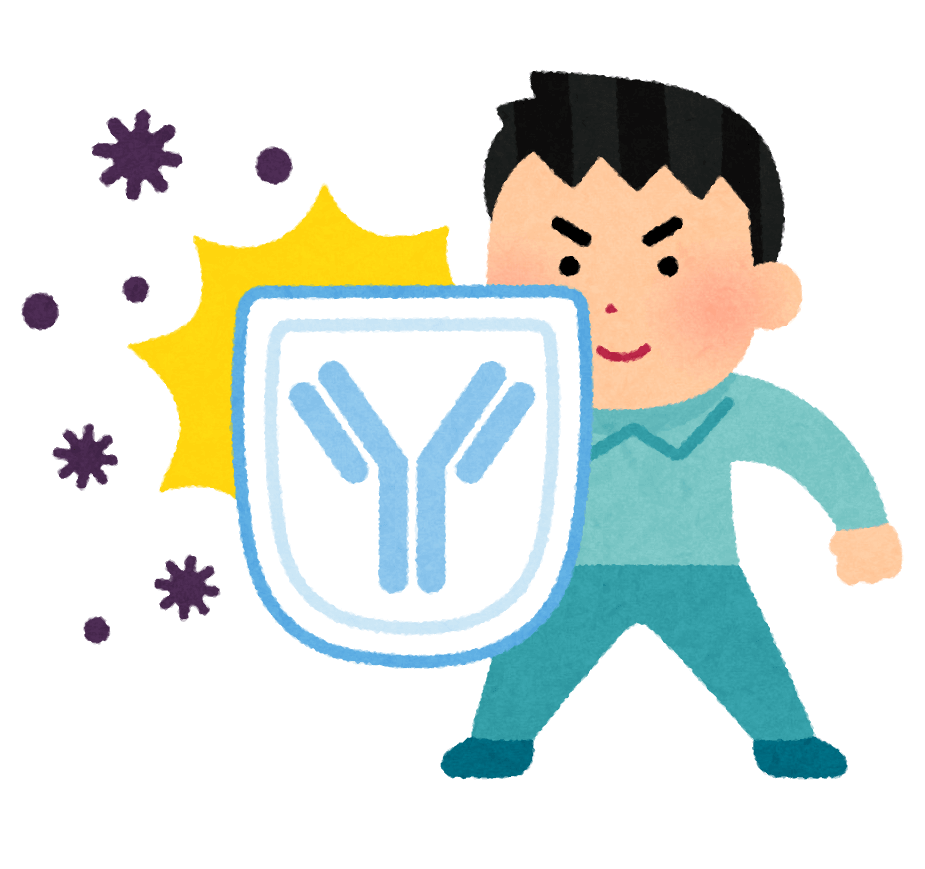
ですからおそらく、対処法は「ルールを始動させないようにする」ことです。最初に相手がルールを始動させるのを許さなければ、私たちはこのルールと直面しないですむはずです。
P.84
返報性の法則からの防衛法の1つが「最初に断る」です。
プロセスを共有していくにつれ愛着が芽生えてしまうのであれば、そのプロセスの入り口の段階で絶っておくことは賢明です。しかしこの最初はなかなかわかりませんし、結構勇気がいるものです。「良さそうな人たし、断って嫌われるのが嫌だな」なんて思ってしまうのでしょう。だからこそ最初の入り口に商談をもちかけてくる人はどこからどう見ても良い人である可能性が高いのです。
もう一つの対処法はもっと有望です。人からの申し出は受け入れるのですが、その申し出がどのような体裁をとっているかではなく、根本的に何であるのかを判断して受け入れるのです。
P.86
返報性の法則からの防衛法の2つ目は「最終的な目的がなにかを知る」ということです。
相手が何を望んでいるのか?をよく観察して知ることが大切です。
「相手が良い人か?それとも悪い人か?」という曖昧なものでは相手の心の内は探れません。終わりを思い描くことから始めましょう。
先に無料情報を提供し、無料点検を行うこの手法によって、防火設備の販売会社はアメリカ中で繁盛しています。
P.88
相手に与えるものは物質的な物に限らず、情報や気持ちといった無形資産の場合が最近増えています。
本当に大切なものは目に見えない、これは本当ですね。
設問
内容の理解1
返報性のルールとは「他人がこちらに何らかの恩恵を施したら、自分は似たような形でそのお返しをしなくてはならない」というルール。
私達の社会でこのルールが強力に作用するのは、このルールを忠実に守らないと重大な社会的不承認を被ることを子どもの頃から教育されてきたから。
内容の理解2
承諾誘導の専門家が利用する返報性のルールの特徴は以下の3つである。
1他の諸要因さえも凌駕してしまう非常に強い力を持っている
2相手を選ばずに適用される
3より大きく不公平な交換を助長する可能性がある
内容の理解3
リーガンの研究では対象者への好感度をも返報性の法則は凌駕する影響力があるのように描かれていた。
内容の理解4
相手の譲歩に返報しなければならないという圧力を使って承諾を引き出すように利用されている。
内容の理解5
取り決めに対する大きな責任感のため同意した内容を実行し、より強い満足感なため将来も進んで親切な行為を行おうとする。
クリティカル・シンキング1
最初に2時間程度時間をもらうことを提案する。拒否された場合は1時間だけの提案を行う。その際にやってはいけないのは一手目に大きすぎる時間設定をしないことである。
クリティカル・シンキング2
一つ目の現象は返報性の法則で受けた恩恵は返したくなる原則が利用されている。
2つ目の現象は受け取った小切手を恩恵として確実に認識した人のほとんどが返報性の法則に適用されたことを証明する結果となる。
クリティカル・シンキング3
ノブレス・オブリージュ(Noblesse Oblige)は直訳すると「高貴さは強制する」を意味し、財力・権力・社会的地位の保持には義務が伴うことを表している。
返報性とは、生まれながらに恩恵を受けている立場にあるものはそれに値する義務なり納税なり何かしら他者に与えなければいけないという法則に適用される点で類似する。
クリティカル・シンキング4
2頭の馬がお互いに毛繕いをしている状態にある。これはどちらが先に毛繕いを始めたのかはわからないが、受けた恩恵はそれ相応の恩を返す返報性の法則が馬においても適用されていることを表している。
以上が第2章「返報性―昔からあるギブ・アンド・テイクだが・・・―」の考察になります。
良くも悪くもやられたらやり返すことが、こんなにも人間社会に浸透していて無意識のうちに影響を受け・与えていたことを自覚することができました。
この影響力を利用して利益を得ようとする者は少なからず存在するので、何か自分の利益になりそうな提案・行為を受けた時はいったん相手の目的を探ってみることを実戦していきたいと思いました。
もっと詳しく読んでみたい!っと思った方はぜひ本書を購入して読んでみてください!
このブログでは紹介できていない事例が沢山乗っていて、深く理解することができます。
次回は第3章「コミットメントと一貫性―心に住む小鬼―」を考察していきます。
それではSee you next time!!

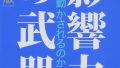

コメント