Q:私達の行動に影響を与えている大きな力はいったい何なんでしょうか?
私達は日々、何かしらに影響を受けて生活をしています。
日常で目にする広告やTV、人の会話など影響を与えるものは多数存在します。
今回は世界的名著である「影響力の武器」を参考に、その正体を一緒に考えていきましょう。
本書はあのメンタリストDaiGoさんが心理学を学ぶきっかけになったという一冊です。
心理学を学びたい人、影響力の武器から自分の身を守っていきたい人などはぜひ本書を購入して読んでみてください。
今回は本書の第3章「コミットメントと一貫性―心に住む小鬼―」を参考に、私の心の琴線に触れた箇所を中心に考察していきたいと思います。
具体的に以下のような疑問・問題を抱える人にはぜひ読んでみていただきたいです。
Q:最近自分が頑固になったなと思ってます。頭が固くなってしまったのでしょうか?
Q:引くに引けない状況が最近あります。どうすればよいのでしょうか?
一貫性のテープが回る
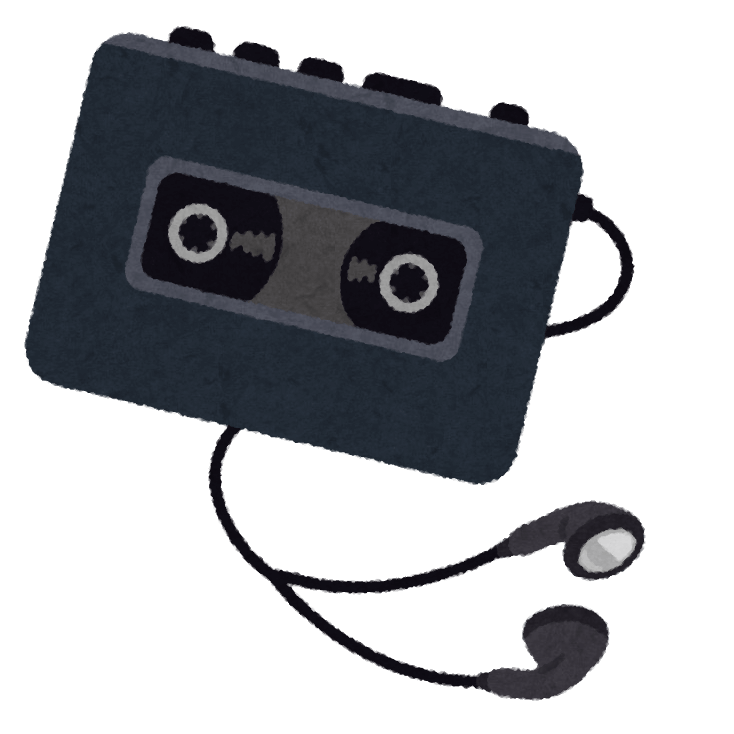
彼らは自分が賭けた馬の勝つ可能性について、馬券を買う直前よりも、買った直後の方が、勝率を高く見積もっていたのです。
P.97
私は競馬を観たことも賭けたこともないので馬券についてはわかりませんが、プロ野球のどこの球団が今年優勝するのかを明言した時なんかは普段よりも賭けた球団の情報を集め、勝率を高めに見積もっているのかもしれません。。
ひとたび決定を下したり、ある立場を取る(コミットする)と、自分の内からも外からも、そのコミットメントと一貫した行動をとるように圧力がかかります。
P.97
自分の内側からは、「過去の自分の決定は間違っていない。もしここで折れてしまうと自分を否定することに繋がってしまう!」として一貫性を保つように圧力がかかり、外側からは「自分が一度公言したことを撤回することは信頼を落としかねないし、ださいな、、」として一貫性を保つように圧力がかかります。
実際、私たちは皆、自分のこれまでの行為や決定と一貫した思考や信念を持ち続けたいと思うあまり、ときには自分をだますことさえあります。
P.98
私が高校生の時、よくONE OK ROCKの「自分ROCK」を聞いていました。
その曲の一節に以下のような歌詞があります。
今日も君は信じること忘れずに目覚められていますか?
時が経つと自分さえも信じれなくなる時代のようです。
自分では気付かないのがこの症状の特徴で、
唯一ある予防法...は「自分にウソだきゃつかない事」
きっと一貫性を保とうとするあまり自分自身の本当の声までもかき消してしまって、自信が持てないような状態になってしまうことがあるのではないでしょうか?
この一貫していたい(一貫していると見てもらいたい)という欲求のせいで、しばしば私たちは自分の利益と明らかに反した行動をしてしまいます。
P.99
偉大なイギリスの科学者マイケル・ファラデーが言ったとされる言葉は、一貫性が時には正しさよりも重視されることを示しています。
P.100
普通だったら優先する利益や正しさまでもを凌駕するこの一貫性の力は恐るべしです。
第一に、ほかの多くの自動反応と同じように、それは複雑な現代生活を営む上で「思考の近道」を私たちに提供してくれます。
P.101
一貫性を保ってさえいれば、考え続ける辛さから逃げられるのです。一貫性テープを再生すれば、多くを考える必要がなくなり、楽に生きられます。
P.102
考えた結果が不快だからという理由で、考えるのを避けることがあります。つまり理論整然と考えると、望んでいない答えがいまいましいくらいはっきりと出てしまうから、精神的な怠け者になるのです。
P.102
第1章で出てきたカチッ・サーの原理と同じように一貫性においても、ほぼ無意識に思考してしまうものらしいです。思考の近道をするということは、思考放棄しているものに近しいのかなとも思います。複雑な世界を生き抜くうえでは必要不可欠な抜け道ですが、使い時にはよく注意したいものです。
悪徳業者は、私たちが要求に対して行う考えなしの自動反応から利益を得ているわけですから、彼らにとって、自動的に一貫性を保とうとする私たちの傾向はいわば金脈です。
P.107
意図的にこの一貫性の原理を使って交渉をしてくる人間・団体は多数存在します。近道と思って通った思考経路の途中には、恐ろしい盗賊が住んでいることはいつでも忘れずに生活していきたいです。
コミットメントが鍵

自分の行動や言葉によって、私たちに一貫性の圧力がかかり、やがて要求を飲まざるを得なくなります。
P.113
「大事なのは、彼らの意志をはっきりさせることです」。この分野の専門家であるスタンコ氏は、客を説得する肝は、コミットメントさせることにあると考えています。彼らはそれを使って、「お客をコントロール」し、利益を得るのです。
P.113
過去に言った発言と矛盾していると「前言っていたことと違う!」といって上げ足をとってくる人はよくいます。だからこそ自分の行動と言葉には注意しておく必要があるのです。もしそうしなければ自分で自分の首を絞める結果になりかねません。そしてこの首元に迫る影を巧みに利用する人がいることも忘れてはいけません。
陪審員候補者の選抜を行うときに、よく考え抜かれた質問を一つします。「もし私の依頼主の無実を信じているのがあなた一人だったとしても、あなたの意見を変えようとする残りの陪審員の圧力に耐えることができますでしょうか?」
P.114
一貫性の法則 VS 他の人からの圧力です。この一貫性の法則があるから自分を保っていられるとはいえ、1人だけ自分の意見が異なっている状況はとても辛く・恐ろしいものです。陪審員の決定にもこの一貫性の法則が考慮されているのだとしたら心理学の偉大さを改めて思い知ることができます。
捕虜収容所のプログラムを検討した結果、中国人がもっぱらコミットメントと一貫性の圧力に頼って、捕虜たちから望ましい承諾を引き出していたことが判明しました。
P.117
中国人の出した答えは至極単純でしたー小さいことから始めて、そこから築きあげよ。
P.117
作文を書いたときに、脅迫も強制もなかったのはわかっているので、多くの場合、そうした状況に陥った人は、実際に行った行動や「協力者」という新しいレッテルと一貫するように自己イメージを変えてしまい、しばしば、もっと協力的な行動をとるようになりさえするのです。
P.118
戦時中に捕虜に対して心理学的アプローチで味方にしてしまう行為を中国は行っていたとされています。人類全てが共通して持っている一貫性の法則を利用して、自国の欠点を多少でも引き出せたら勝ったのも同然なのです。ここでは作文を利用して、中国側を肯定する内容を引き出し、それを他の捕虜にも公示することで外圧からも一貫性を保つように仕向けています。戦争に心理学が用いられていて、しかもそれが効果抜群な結果を得ているのは驚きしかないです。
承諾に関心をもつほかの人たちもこのやり方の有効性に気づいています。たとえば、慈善団体は、段階的にコミットメントを強めていくことで、より大きな要求を飲ませる方法を用います。
P.118
最初に小さな要求を飲ませ、それから関連するもっと大きな要求を通すというやり方には、「段階的要請法」(フット・イン・ザ・ドア・テクニック)という名前がついています。
P.119
最初はたわいもないぐらい小さく、すこしずつ大きくしていくテクニックは「段階的要請法」とも呼ばれているらしいです。少しの善行は次第にとてつもない大きな善行に繋がるので最初の一歩は警戒しておいた方がよさそうですね。とは言ってもとてつもなく小さな要求であったら気付かないのかもしれませんが、、、
このやり方はただ顧客に自分の選択を言明させているだけではないからです。なぜそれを選ぶのかという理由をはっきり言わせています。そして、第1章で見たように、人は時として理由があるからという理由だけで行動するものなのです。
P.121
コミットメントにより大きな力を加えるとしたらやはり理由付けが良いのかもしれません。理由のありなしでは一貫性の強さが異なってきそうです。ダイエットをするにしても、ただなんとなく痩せたいからという理由よりも「夏に海で水着を着て遊びたい」みたいな具体的なイメージのある理由の方が効果がありそうです。
最初に応じたささやかな依頼とはほとんど関係のない、さまざまな種類の大きな依頼を受けやすくなるかもしれません。
P.122
つまり、他者の自己イメージを操作するためには、小さなコミットメントが利用でき、それを使えば、市民を「公僕」に、見込み客を「顧客」に、捕虜を「協力者」に変えることができるのです。
P.123
上記2つはどれも段階的要請法の例ですが、最終目的を明確にされた場合私達はどのように最初の一手をみわければよいのでしょうか?
望むような形に相手の自己イメージを変えることができれば、その人は、新しい自己イメージと一貫したあらゆる範囲の要求を自然と受け入れるようになります。
P.124
「男にはデータを、女にはイメージを売れ」という言葉は聞いたことありますか?今回でいうとイメージの方に注力されていますが、理想のイメージをひたすらさせて落とすのはよくあるテクニックですね。夢とか理想とかは使い方を間違えると簡単に深く厳しい落とし穴に落ちてしまうのです。
人は自分が外部からの強い圧力なしに、ある行為をする選択を行ったと考えるときに、その行為の責任が自分にあると認めるようになります。
P.150
子どもに何か本心からやらせようと思うなら、決して魅力的なご褒美で釣ったり、強く脅してはいけないということが言えるでしょう。
P.151
コミットメントが効果的に影響を及ぼすためには、いくつか条件がそろっていなくてはいければなりません。行動を含むこと、公表されること、努力を要すること、自分の意志で選ぶこと、です。
P.124
最後の「自分の意志で選ぶこと」がとても気に入りました。他人に強要された行動ではなく自分から自主的に選択した道であれば確かに一貫性の威力は強くなりそうです。まさに意志あるところに道があるですね。
人の本当の感情や信念は、言葉よりも行動によく表れます。他者がどのような人なのかを判断するときには、その人の行動をよく見るものです。
P.125
BadManの映画を先日観たのですが、こんなシーンを想い出しました。
「内心がどうあれ、行動が本性を決めるのよ」
まさに本質をついたセリフだと思います。
作文は中国人が絶え間なく捕虜に促したコミットメント行動の1つです。捕虜が中国側の主張を黙って聞き、さらには口頭でその意見に同意したとしても、まだ足りなかったのです。
P.126
文章という取り消しがきかない形で記録された行動のせいで、捕虜は自分が確かにしてしまったことと一貫性を保つように信念や自己イメージを変えざるを得なくなりました。
P.127
人には、書かれた意見は書いた人の本心を反映しているとみなす生来の傾向があります。この傾向の驚くべき点は、文章の作者が自由に意見を書いたわけではないと知っていても、やはりそう考え続けるというところです。
P.127
中学生の頃、学校でトラブルが発生すると反省ノートを先生から渡され交換日記のように作文を書かせる慣習がありました。これは目に見えて本人の手で書かれたものであれば他の人はそれを本人の意思だと思い、外圧からして書いた通りの行動をするように本人が成り立っていくことを利用していたのだと今になって振り返ります。
誰かが自分を慈悲深い人間だとみなしている知識が、その見方と一致した行動をその人たちにとらせることになったわけです。
P.128
この手のお世辞によって、相手の気分をよくしただけではなく、相手の自己イメージと自分が目指す目標の達成に役立つ相手の行動を結びつけたのです。
P.128
自分の内側からは、自己イメージを行動に合わせようとする圧力がかかります。そして外側からは、もっと密かな圧力ー他者が自分に対して抱いているイメージに、自己イメージを合わせようとする力ーが加わるのです。
P.128
相手からどう思われているかに合わせて自分の行動を変えてしまうのが人間らしいです。良い人というレッテルを貼られたら良い人として行動を行い、賢い人と言われたら賢い人のように行動するなどです。まるで魔法のように相手を服従させる力が言葉やイメージにはあるのですね。
他のプロたちも、意見を書くというコミットメントの力を知っています。たとえば、大成功をおさめているアムウェイ社には、販売員たちがさらに業績を伸ばすよう促すための方法があります。販売員たちに販売目標を設定させ、その目標を紙に書かせるのです。
P.130
意見を書かせることで、それを書いた本人が本当に変わってしまう理由の1つは、書かれたものが簡単に公表できてしまうという点にあります。
P.133
このパブリック・コミットメント戦術は、プライドが高い人、あるいは公的自意識が高い人に特に有効なようである。
P.137
私が勤めている会社でも、上期下期で目標をそれぞれ記し達成に向けて努めるような仕組みを導入しています。これもコミットメントと一貫性を利用したものになりますね。
コミットメントに労力が投入されればそれだけ、コミットした人の態度に与える影響が強くなります。
P.138
「何かを得るために大変な困難や苦痛を経験した人は、苦労なく得た人よりも、得たものの価値を高く見積もるようになる」
P.145
海兵隊員だった知り合いはみんな、あの苦しい訓練のおかげで、自分が強く、勇敢で、よりよい人間に生まれ変わったと思っている。
P.147
優秀で結束した集団を維持させることに腐心する集団の場合、苦痛を要求するような加入儀礼は簡単にはなくならないようです。
P.148
私は高校生の時野球部に所属していました。そこではどの部活よりも厳しいと自負していた練習が日々ありました。当時はほとんどが苦しい経験のみとして記憶していましたが、今振り返るととても貴重な経験をさせてもらっていたとつくづく思っています。
またボーイスカウト活動をしていた時には、昇格の際に皆から足をネッカチーフで叩かれて祝福される儀式がありました。これも一種の通過儀礼で、よりその組織へのコミットメントを強めるものだったのだと今振り返っています。このような儀式はやはり仲間と共に経験することでより絆も深まるものだとポジティブにとらえています。
「自分の意見に反して賛同した者は、元の意見を持ち続ける」
P.156
なるほど、と思いました。きっと心の中にしまっておいて塩漬けにした意見は墓場まで持っていくことになるのでしょう。自分の意見を主張することは自分のためにも大切にしていきたいです。
この自らを補強するコミットメントは、理由を新たに付け加えながら成長するという点が重要です。そうした行動をとるきっかけとなった元々の理由がなくなったとしても、新しく発見された理由があるため、自分の行動が正しかったと考え続けられるのです。
P.157
雪だるま式に自分を肯定する意見を集める習性が人間にはあるみたいですね。そうすることで自分を保っている人が多くいるようにも思えます。自分の価値観を否定する意見にも耳を傾けることは大切になってくるのではないでしょうか?
承諾先取り法には様々な種類がありますが、基本的な手口はどれも同じです。まず相手にとって有利な条件を提示し、喜んで買うという決定を誘い出します。そして、決定がなされてから契約が完了するまでのあいだに、もともとあった有利な購買条件を巧みに取り除くのです。
P.159
一度承諾してしまったら後には引けない人間の心理は巧みに利用されます。条件をしっかりと確認した上で承諾をすることが大切です。
防衛法
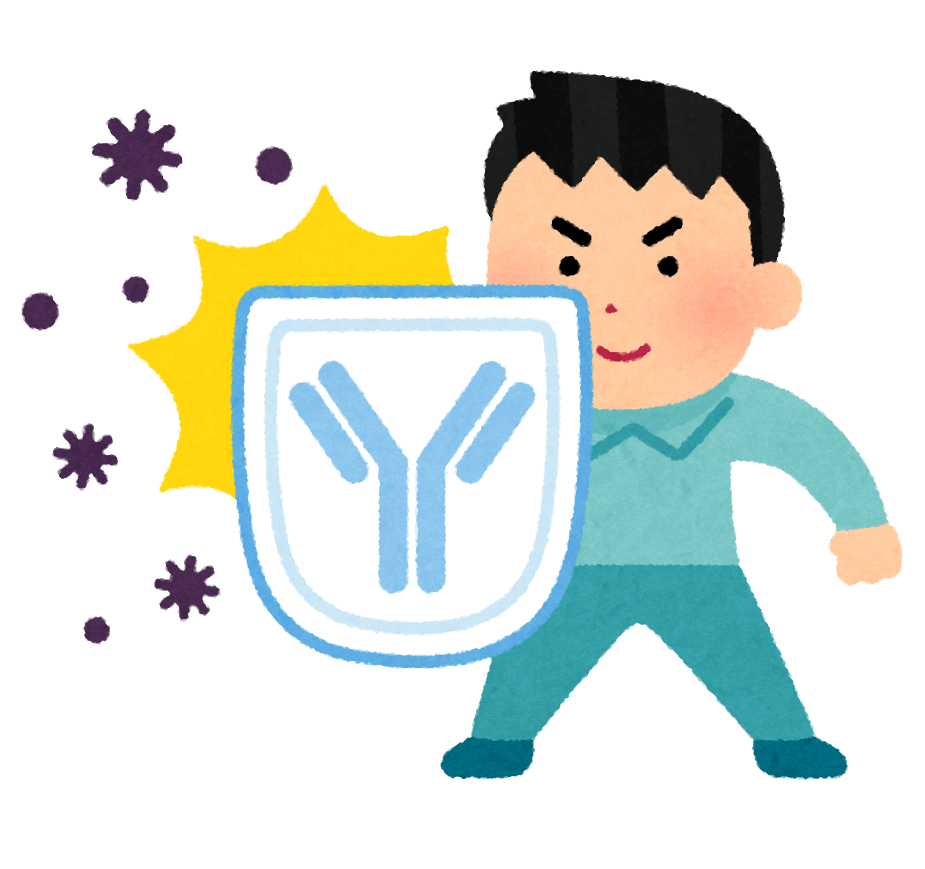
人間には、危険で機械的な種類の一貫性さえも必要なのです。このジレンマから抜け出す唯一の方法は、そのような一貫性が不利な選択を導きがちなのは、どんな時かを知ることです。
P.167
どんな時でしょうか?きっと相手が何かしらメリットを得る時ではないでしょうか。
心理学的な研究は、人が行う知的判断に一瞬先だって、感情的な反応が生じることを示しています。私が思うに、心の奥底からのメッセージは、純粋な本音の感情です。
P.174
違和感。この言葉を一瞬体で感じ取ったら危険信号が出ていることに気づいていきたいです。
当然といえば当然ですが、考え方や行動の一貫性を人並み外れて保とうとする傾向がある人びとは、往々にして、一貫性の法則をつかった戦術の犠牲者になってしまいます。
P.177
一貫性へのこだわりは年を重ねるにつれて強まり、五十歳を超えた人たちが最も強く、以前にしたコミットメントとの一貫性を保とうとする傾向を示すとわかったのです。
P.177
自分は我を通そうとするところがあります。特に自分がマイノリティだと自覚した際には、なお一層自分の意見を貫こうとします。だからこそ一貫性の罠にはまってないかをチェックする必要はありそうです。
個人主義者はある状況で何をすべきか決めるのに、まわりの人の経験や意見、選択を参考にするのではなく、まずは自分の過去の体験、これまでの意見や選択を振り返ります。
P.179
したがって、個人主義的な社会メンバーは、ほんの少しのステップを求めるところから始まる影響戦術に、警戒しなければいけません。
P.180
自分はどちらかというと個人主義的な側面があります。だからこそ一貫性の戦術を利用してくる人には気を付けていきたいものです。
設問
内容の理解1
第一に、一貫性を保つことによって、社会から高い評価を受ける。第二に、一貫性のある行為は、一般的に日常生活にとって有益である。第三に、一貫性を志向することで、複雑な現代生活をうまくすり抜けるのに役立つ、思考の近道が得られるため。
内容の理解2
一貫性には自分の内側・外側両方面から圧力がかかる力があるため
内容の理解3
行動を含むこと、公表されること、努力を要すること、自分の意志
内容の理解4
文章を書くという行動を伴い、書いた書物が公表され、思考や動作の努力が必要とされ、書物は書いた本人の意思を反映するものであると周囲はみなす傾向にあるため
内容の理解5
一度コミットメントを行うと、その後自分の決定に対する正当性を示す理由をを付け加えるようになり自分を支える柱を築く。そのため承諾先取り法のように、先に意思決定をさせた後に諸条件を抜いたとしても、意思決定者は自分の意見を正当化しているため意見を変えることはない。自分を支える最初の柱ができた後に、新たな柱がいくつも出来上がって、最初の柱がなくても支えることができるようになってしまっているのである。
クリティカル・シンキング1
個人の意見を主張するのではなく、よく周囲の意見と自分の意見を見比べて足並みをそろえて全体主義としてふるまうこと。自分の最初の意見に固執せずに、意見を変えることも厭わないようにすること。
クリティカル・シンキング2
胸にタトゥーを入れることで、タトゥーを刻む行為・皆に見られて公表・タトゥーを入れる際の忍耐的努力・タトゥーを入れる決心をする意思の4条件が加わるため、コミットメントの力は最大化し、別ブランドへの心変わりはしなくなる。
クリティカル・シンキング3
習字で自分が勉強することを書き、それをSNSにアップする。そうすることで周囲に自分が勉強をする意思を公表することになるためコミットメントの力が強く働く。
クリティカル・シンキング4
結婚式を行うことで、周囲へ結婚することの意志を公開することになる。また結婚式には準備(行動・努力)が必要になり、よりコミットメントの力が強く働き別れづらいように一貫性が働く。
クリティカル・シンキング5
最初に断わらずにお願いを承諾してしまったために、少しずつ承諾のレベルとコミットメントの力が上がり、最終的には嫌なお願いごとに対しても半強制的に参加せざるを得ない状況に落ちってしまう。そのため、最後に断るには多大な勇気と努力が必要になるので、最初の小さなお願いの段階で断っておくことほうが簡単になることを示唆している。
以上が 第3章「コミットメントと一貫性―心に住む小鬼―」 の考察になります。
一貫性の法則は社会で生きていく上で必要不可欠なものであることはわかりました。
自分の意見を保っていなくて、すぐに意見を変える人は信用されません。一方で、強すぎる一貫性のせいで本質的に大切なことがらをも凌駕してしまっては本末転倒になります。
ちょっと自分頑固かな、、、と思った時こそ冷静に自分の意見や他の人の意見を混ぜて再検討し、場合によっては方向転換をしていく必要がありそうです。
そしてもっと詳しく知りたいと思った方はぜひ本書を購入して読んでみてください!
このブログでは紹介できていない事例が沢山乗っていて、深く理解することができます。
次回は第4章「社会的証明―真実は私たちに―」を考察していきます。
それではSee you next time!!
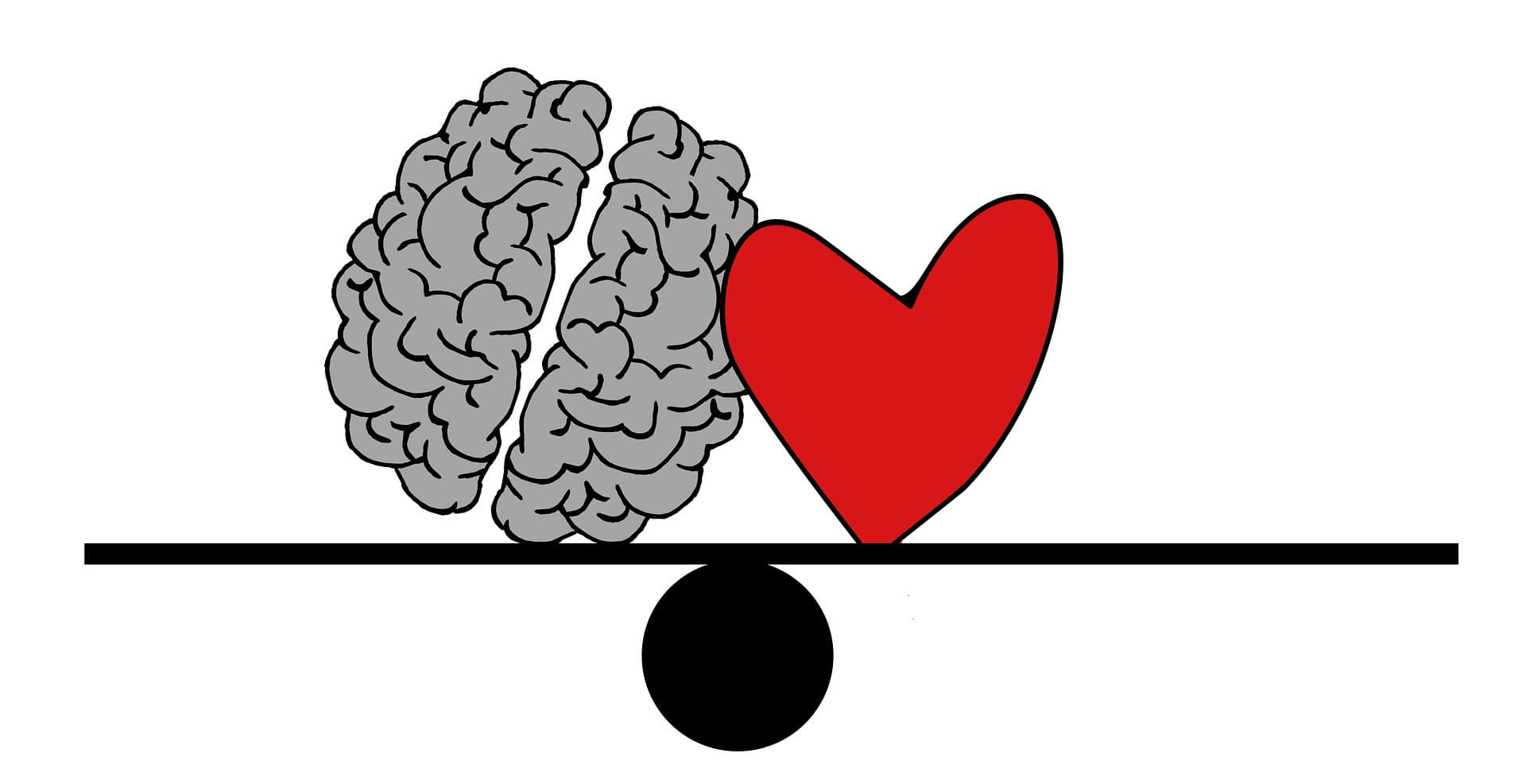


コメント