Q:私達の行動に影響を与えている大きな力はいったい何なんでしょうか?
私達は日々、何かしらに影響を受けて生活をしています。
日常で目にする広告やTV、人の会話など影響を与えるものは多数存在します。
今回は世界的名著である「影響力の武器」を参考に、その正体を一緒に考えていきましょう。
本書はあのメンタリストDaiGoさんが心理学を学ぶきっかけになったという一冊です。
心理学を学びたい人、影響力の武器から自分の身を守っていきたい人などはぜひ本書を購入して読んでみてください。
今回は本書の第4章「社会的証明―真実は私たちに―」を参考に、私の心の琴線に触れた箇所を中心に考察していきたいと思います。
具体的に以下のような疑問・問題を抱える人にはぜひ読んでみていただきたいです。
Q:お笑い番組で自分は面白いと思わないのに、周りの人は笑っています。私がおかしいのでしょうか?
Q:道端で倒れている人がいましたが、周りが特に気にかけていなかったのでスルーしてしまいました。後に急病患者だったことがわかりました。スルーした私がいけなかったのでしょうか?
Q:ウェルテル効果とはなんでしょうか?
社会的証明の原理

お笑い番組であの笑い声を使えば、ネタがつまらないときでも(いや、そうしたときにこそ)視聴者のウケがよくなるというわけです。
P.188
ここでいう笑い声は事前に録音されていた笑い声のことを指しています。芸人のネタに合わせてベストなタイミングで笑い声を追加することで視聴者に「ここは笑うところなんだ、笑っていいんだ」と思わせて笑いを誘うことができるというわけです。
この原理が特に適用されるのは、どう行動するのが正しいかを決めるときです。特定の状況で、ある行動を遂行する人が多いほど、人はそれが正しい行動だと判断します。
P.189
「皆が賛成していることだからそれは正しいことだ」と盲信することこそが社会的証明の本質です。私はこの文を読んだときに某ドラマを思い出しました。
賛否両論あると思いますが、司法の決定を民意に委ねるようなことがあってはならないと個人的には思います。台詞にもある通り「人は見たいように見て、聞きたいように聞いて、信じたいように信じる」のです。この行動自体は誰にでもあることなので否定はできませんが、そのような曖昧な感情を伴ったものを天秤の片方に置くのは実に不公平極まりない状況なはずです。皆さんはどのように考えますでしょうか?
みんながやっているなら、その行為は正しいと仮定する私たちの傾向は、いろいろな場面で悪用されています。
P.191
「自分で何を買うか決められる人は全体の5%、残りの95%は他人のやり方を真似する人たちです。ですから、私たちがあらゆる証拠を提供して人びとを説得しようとしても、他人の行動にはかなわないのです。」
P.192
意志がない、と自己否定された経験はありませんか?その発言をした人はきっとさも自分には確固たる意志があって行動しているかのように自負しているのかもしれませんが、実はその発言者も他の人の影響を大いに受けて生活しており「あなたの意志はどちらに?」と聞き返してあげたくなりますね。
子どもが何を適切と考えるかについて、映像作品が与える大きな影響は、テレビで頻繁に暴力的な場面や攻撃的な場面が流されることを憂慮する人びとにとって、大きな悩みの種となってきた。
P.195
他人の行動から影響を受けるのは何も周囲の人間関係からだけではないみたいです。TVや映画などに登場してくる人たちからも影響を受けているのです。TVに関しては確かに暴力シーンがかなり減少してきているのではないでしょうか。暴力シーンはかなり刺激的でもしかしたら視聴率をとれるシーンなのかもしれませんが、ここからは倫理や人間性の育成との天秤をかける世界になっていきます。
しかし歴史は、預言が外れたとわかった直後から、彼らが謎の行動をとることを示しています。カルト信者たちは、幻滅し、集団を解散するのではなく、しばしば信仰を強めるのです。
P.196
グループのメンバーは、自らの信念のためにあまりに多くのものを犠牲にしており、もう後戻りできないところまで来ていたので、その信念が崩れ去っていくのを見ていられませんでした。
P.206
物理的証明によって、唯一の真実だと受け入れていた信念が否定されてしまった以上、彼らが窮地から抜け出す方法は1つしか残されていませんでした。信念の正当性を支持する別の証明、すなわち、社会的証明を打ち立てることです。
P.207
これらの文章はカルト集団が信じていた預言が外れた後に、社会的証明によって自分達を正当化するために今まで行ってこなかった布教活動を開始した事例を取り上げています。
この事例を読んだとき、ふと高校時代のある定説を思い出しました。それは「最後まで部活動に打ち込んでいた学生はその後猛烈に勉強し、難関大学に合格する傾向にある」というものでした。野球部・サッカー部・バスケ部など多くの体育会系部活動は高校3年時まで大会がありますので、それまでは勉強に専念できていません。それでも最終的には難関大学に合格できるのはもしかしたら難関大学に合格することで、儚く引退してしまった部活動を正当化しようとしていたのではないでしょうか?確かにスポーツをやっていたため培われた根性や自頭の良さ等要因は多数あると思いますが、少なからず自分達が行ってきた活動を社会的に認められている大学(難関大学)に合格することで正当化しようとしていた可能性はあります。
まあ、原因がなんであれ難関大学に合格して次のステージでまた活躍の場を広げられているのだとしたら良いように思いますが(笑)
どんな考えでも、それを正しいと思う人が多ければ多いほど、人はその考えを正しいと見ることになる。
P.208
どんな考えでも、というのが恐ろしく感じました。共感を含む考えがあるからこそ、ある意見を正しいと認識するのだとは思いますが、特に善悪を自分で判断しづらい場合においてはマジョリティの意見が正しいと決めつけるのは思考停止に陥っている状態で、危険をはらんでいます。
死因は…不明(確なこと)
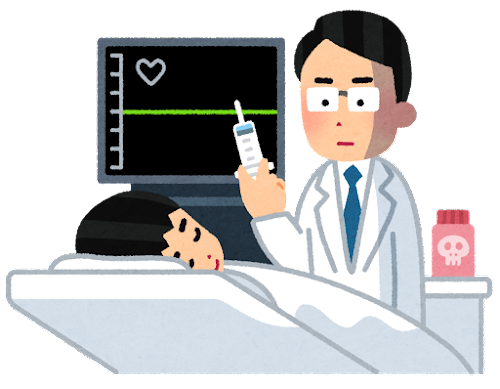
本書で扱う影響力の武器はどれも、ある条件がいくつか加わると、一層効果的に機能します。もし、こうした武器から身を守りたいなら、それがうまく機能する最適の条件を知ることが重要となります。
P.208
第2章返報性においては相手の善行がトリガーでした。
第3章一貫性においては行動、公表、努力、意志の4要素が条件でした。
では第4章社会的証明においては何が条件になるのでしょうか?
改宗者を求める気持ちに火がついたのは、自分たちの確信がぐらついた時でした。
P.208
不確かさが生まれるもう一つの条件は、状況に対する馴染みのなさです。
P.208
本節の冒頭で、不確かさの発生条件が述べられています。「確信のぐらつき」と「不馴染みさ」が条件みたいです。
しかし、なんといっても多かったのは、「巨大都市の社会」や「個人が集団から疎外されること」が都市生活を「非人間的なもの」にしているという指摘でした。
P.213
そして我が身を守る唯一の方法は、彼らをできる限り無視することであろう。隣人や、彼らのトラブルに対する無関心は、ニューヨークのーそして、それ以外の大都市のー生活において条件反射なのである。
P.214
不確かさにより集合的無知(後述)という現象が生じたジェノヴィーズ事件について紹介されており、都市生活の危うさを指摘しています。
第一の理由は、わかりやすいもので、助けられそうな人がほかに何人かいれば、一人ひとりの個人的な責任は少なくなるからというものです。
P.215
第二の理由は、もっと心理学的に興味深いものです。これは社会的証明の原理に基づいたもので、集合的無知の効果が含まれているからです。
P.215
他に多数人がいる場合、緊急事態に陥っている場面に遭遇しても、人助けをしなくなる傾向が生じやすくなる2つの理由を説明しています。それは「責任分散」と「集合的無知」によるものだと筆者は説きます。「自分が助けなくても大丈夫だろう」という気持ちや「皆がお互いに気持ちの探りあい」を行って正しい判断ができない状態がおきてしまうということです。
「そのとき人は、誰も関心を払っていないのだから、悪いことは何も起こっていないのだ、と判断してしまう。」
P.216
集合的無知の効果は、見知らぬ人同士のあいだで最も強く現れるようです。
P.218
肝心な点は、人が集団になると援助しなくなるのは、彼らが不親切だからではなく、確信がもてないからなのだと、ちゃんと理解することです。
P.221
これまで見てきた研究結果に基づいてアドバイスをするなら、群衆から一人の人間を分離しなさい、ということになります。その人だけを見つめ、話しかけ、まっすぐに指をさし、ほかの人は無視するのです。
P.223
集合的無知について説明をしています。集合的無知は互いが知らない人同士の集団であると効果が強いとのことです。
普通自動車免許を取得する際、講習のいっかんで救急車を呼ぶ集合研修がありました。その際、自分は人口呼吸等措置を行い、救急車を呼ぶのは周りにいる人の中から指さして指定するように強く言われたことを覚えています。教官曰く、「誰か救急車を呼んでください!」だけでは、誰も救急車を呼ばない&救急車を呼ぶ時間が遅くなるとのことで説明を受けました。これは集合的無知と関係があるのではないでしょうか?「誰か、は私ではないのできっと他の見知らぬ誰かが救急車を呼んでくれるはず。ここで私が変に救急車を呼ぶ必要はない」と思う人がほとんどなのでしょう。こういった事例が沢山報告されている?からこそ、教官は個人を特定して指示するように強く主張したのでしょう。皆さん、救急車を呼ぶ状況にあったら自主的に行動して命を救いましょう。
私のまねをしなさい…サルのように

社会的証明の原理にも、その効果が強くなるいくつかの条件があります。その一つが不確かさです。どう振る舞えばいいのか確信がもてない場合に、人が普段よりも一層、他者の行動を参考にして自分の行動を決めるようになるのは、間違いありません。
P.226
不確かさーこれは社会的証明の原理の相棒です。
P.246
もう一つ重要な条件があります。類似性です。社会的証明の原理は、自分と似ている人の行動を見ているときに最も強く作用します。
P.226
人が最も疑問を感じずに真似をしてしまう相手は、自分と似た他人です。
P.246
社会的証明の原理、発動条件は「不確かさ」と「類似性」です。VUCA時代に突入し、コロナウイルスの萬栄に伴い、将来に対する「不確かさ」が増していますので、より一層「類似」する人(年代・性別・性格・出身等)を真似する人が増えていきそうです。
現代生活では常に多くの人が精神的な苦痛を抱えて生きています。そして、人がその苦痛にどう対処するかを決めるのには、多くの要因が関わりますが、そうした要因の1つが、自分と同じような他者がその苦痛にどう対処しているか、なのです。
P.242
最近開発したいアプリを思いつきました。「コンプレックスマッチング」という名で、同じ苦しみを持つ人同士だけが入れるコミュニティを形成し、そこで様々な問題解決に対する情報共有を行うのです。そうすれば問題を解決できるだけでなく、苦しみを分かち合うことができるのではないでしょうか?そしてそこでカップルが成立すればそれもなお良しな感じがします。
広告主は、商品を普通の視聴者に売り込むには、ほかの「普通の」人びとがそれを好んで使っていることを示せばいいとわかっているのです。
P.226
CMで有名タレントを採用することも効果的ではありますが、実際の消費者と「類似」する人を採用することで社会的証明の原理を発動させることができます。
むしろ、自殺報道そのものが、自動車や飛行機の事故を生み出しているのです。
P.232
一人だけの自殺の新聞記事の後、増加するのは一人の事故死の件数だけで、別の人間を巻き込むタイプの自殺が報道された後、増加するのは複数の死者が出る事故だけなのです。悲嘆だけが原因なら、こうしたパターンが生じるはずはありません。
P.233
彼はこうした現象が「ウェルテル効果」と呼ばれるものによって説明できると確信しています。
P.233
他人の自殺を知ると、残念ながら大勢の人たちが、自分にとっても自殺が適切な行動だと考えてしまいます。そして、そのなかの何人かがためらいもなく直接行動に移り、自殺率を増減させてしまうというのです。
P.234
TVで頻繁に放送される暗いニュースの数々、特に死に関係する事柄についてはウェルテル効果が働き、同じパターンの死が発生するとのことです。暗いニュースに伴い発生する「不確かさ」と被害者が「類似」する人であった場合は要注意です。個人的にはこういった類の暗いニュースはたとえ真実であったとしても、大々的にピックアップして放送する必要はないと考えています。しかし、人は生存本能が働き不安や恐怖に目がいくため視聴率がとれやすいのも事実ではあるのではないでしょうか?マスメディアは大きな力があるだけに、もっとよく考えていく必要があると思います。
彼の発した力は、並外れた個人の資質よりもむしろ、基本的な心理学の原理を理解していることに由来していると、私は考えています。
P.248
リーダーとして見た場合、彼が本当に優れていた点は、1個人のリーダーシップの限界を知っていたところです。いかなるリーダーでも一人の力だけで、集団のメンバー全員を常に従わせることはできません。
P.248
集団のかなりの数のメンバーが納得したという生の情報が、それ自体、ほかのメンバーを納得させるのです。したがって、最も影響力のあるリーダーというのは、集団の状況をどう整えれば、社会的証明の原理が自分に有利に働くようになるかを知っている人なのです。
P.248
社会的証明の原則により起きた事件の中で本書では「ガイアナのジョーンズタウンでの集団自殺」が紹介されています。とある団体の指導者ジム・ジョーンズ師が集団を引き連れて南米のジャングルに引っ越し、そこで集団自殺が行われていたのです。この事件でもやはりジャングル内という「不確実さ」と同じものを信じる「類似性」がトリガーとなり社会的証明の原則が発動し、一人目に選ばれし者が自殺を行うと他の者も続いて連鎖的に自殺を行うようになっていったのです。
この事件は一人のリーダーによって導かれたものでしたが、そのリーダー性は上記引用したように心理学の基本原則にのっとったものであることがわかります。
自分の身を守るためにも、このような事例があることは知っておく必要があると思いました。
防衛法
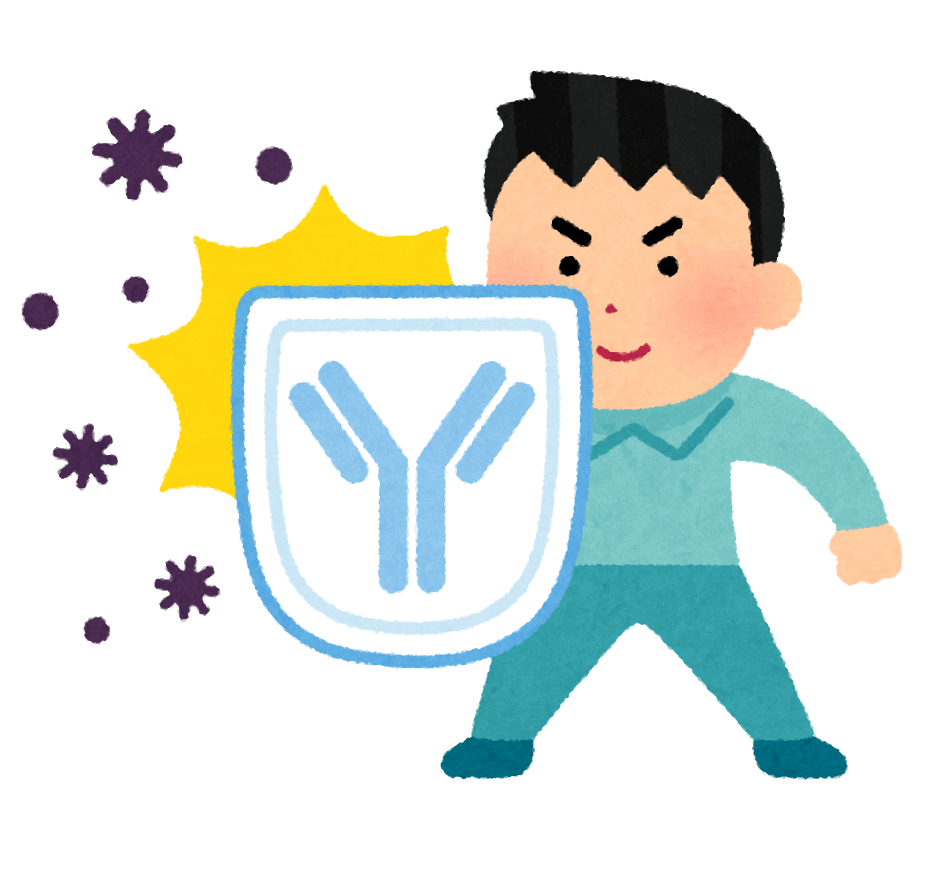
どう振る舞うべきかを示す証拠というのは、たいてい正しく価値があるものです。それがあるおかげで、私たちは賛否両論を詳細に吟味することなしに、自信をもって星の数ほどある決定をしていくことができます。この意味で、社会的証明の原理は、多くの飛行機に装備されているような自動操縦装置を私たちに提供してくれているのです。
P.249
自動操縦が支障をきたすのは、主として不正確なデータが装置に入力された場合なのですから、こうした事態に対処する最良の防衛法は、どういう時にデータが誤るのかを知ることです。
P.250
返報性・一貫性と同じく、社会的証明の原則も生活をしていく上で必要な役割を担っています。だからこそ、データの誤りや錯覚を見抜いていけるようになるしかないのかもしれません。
二人は、単なるオペラの常連というばかりではなくビジネスマンでもあり、その商品は「拍手喝采」でした。
P.251
サクラもスペシャリストを生み出すようになりました。たとえば、泣き手には、合図があり次第すぐに泣けるという能力をもった人が選ばれ、叫び手は、じつに興奮した声で「もう一度」とか「アンコール」と叫ぶことができました。
P.251
エンタメはオーディエンスが完成させる、と秋元康さんもおっしゃっていましたが、エンタメの現場ではこのようなサクラは多数存在するのではないでしょうか?
コンサート会場は多くのお客さんにとって、どう振る舞っていいのかわからない場面が多数存在します。黙っておくべきなのか?咳払いするべきところなのか?スタンディングオーベーションをするところなのか?などです。だからこそエンタメの会場においては観客を先導する役割は必要になってくると個人的に思います。
広告に登場する人たちを「火星からの消費者」と呼んでいる。
P.255
ここでいう「火星からの消費者」とは路上インタビューに登場する素人の振りをしたサクラのことを指します。そして「火星からの消費者」は企業側に良いようなコメントをして立ち去っていくのです。「嘘を嘘であると見破る必要がある」と2チャンネル開設者ひろゆき氏は話していますが、今の口コミコメントは見破るのは厳しい状態にあるのではないでしょうか?
悪気のない自然な過ちが雪だるま式に多くの社会的証明を生み出し、それが私たちを誤った決定に駆り立てるのです。緊急事態の場面に居合わせた人たちが、心配することはないと思ってしまう集合的無知の現象は、この過程の一例です。
P.257
多くの人びとが同じことをしていると、私たちは自分が知らない何かを彼らが知っているに違いないと思ってしまうのです。特に自分で確信がもてないときには、群衆の集合的知識を過度に信用してしまいます。
P.258
群衆の示す行動は誤りであることが非常に多いのです。なぜなら彼らの行動はなんらかの優れた情報に基づいているわけではなく、彼ら自身もまた社会的証明の原理に反応しているだけだからです。
P.258
民意は本当に一人一人が考え抜いたものであるのかどうかをまずは疑ってみる必要があります。民意が何の影響を受けているのか?インフルエンサーは誰なのか?そういったことを推測したり、証拠を見つけたりすることで見る目は養われていくのではないでしょうか?
極東社会の人びとは、西洋文化に暮らす人びとと比べ、社会的証明のもたらす情報に反応する傾向が非常に強い。しかし、個人よりも集団に重きを置く文化ならどこであれ、同胞の選択に関する情報から、人びとはより大きな影響を受けるのだ。
P.259
群衆が示す証拠に自分が釘付けになっている時には、周囲を定期的に見わたす必要があります。
集団主義の場合、特に日本なんかは多くの場合そうですが社会的証明の罠には要注意ですね。冷静に、定期的に周囲を見渡してみましょう。
設問
内容の理解1
社会的証明の原理は、人がある状況で何を信じるべきか、どのように振る舞うべきかを決めるときに重視するのが、ほかの人びとがそこで何を信じているか、どのように行動しているかであることをいう。
録音された笑い声を使うと、笑うべきシーンかどうかが明確になるため、録音された笑い声につられて観客も笑うようになる。
内容の理解2
預言が外れたため、改宗者を増やし社会的に認められることで自分達が信じているもの・行為を正当化しようとしたため。
内容の理解3
不確かさと類似性である。
ジョーンズタウンでは上記2条件が整ったため、選ばれし一人目の自殺者に続いて集団自殺が行われた。
内容の理解4
集合的無知とはある集団が互いに行動を確認しあって判断した結果、実際の問題となるものに無知な状態なまま放置をしてしまうことである。
集合的無知があるため緊急事態に居合わせた人びとに、その場は問題ないと錯覚させてしまう。
内容の理解5
都会で培われた周囲の人間に対する無関心さによって、集合的無知が形成され、介入をはばむ。
内容の理解6
ウェルテル効果とはマスコミの自殺報道に影響されて自殺が増える事象のこと。
奇妙なことに一人だけの自殺の新聞記事の後、増加するのは一人の事故死の件数だけで、別の人間を巻き込むタイプの自殺が報道された後、増加するのは複数の死者が出る事故だけというパターンが存在する。
クリティカル・シンキング1
集団がいたら、その中の特定の人物を指定し身体的特徴や服装などを明確にして救助の指示をだす。間違っても集団全体に対して救助を求めることはしてはいけない。
クリティカル・シンキング2
異物混入という「不確かさ」と、被害者がニューヨーク在住の女性という特定されており他のニューヨーク在住女性にとっては「類似性」があてはまり、社会的証明の原理が発生する。またこの事件が広く報道されてしまったために、少なからず影響を受けてしまう人がいることからタイレノール事件後の進展も予測できたかもしれない。
クリティカル・シンキング3
まずウェルテル効果という現象があることを説明する。
その後、自殺をしようとしたことがあるがくいとどまった経験のある人(対象者と同年代)にインタビューした動画を対象者に見せて、どのようにしたら苦しみを乗り越えられるのかを考えてもらい、命の大切さを説く作文を記載し、インターネットで公表する。
質問としては「何が苦しい原因となっているのか」を聞き、同じ悩みを持つ視聴者に生き続けることを訴える。
クリティカル・シンキング4
コンテスト運営を行っていた際に、採用人数を5人にするか6人にするかでもめた。
その際に5人派リーダーの人が裏で友人たちに自分に賛同する意見を述べるように働きかけていたため、5人派が多数のように見えた。そのためどっちでも良い派は多数派につく結果となった。
今ならゲリラ的に投票を行い、裏工作がない状態での投票を実施する。
クリティカル・シンキング5
冒頭の写真はファーストペンギンに続き、エサを求めて海に飛び込むペンギンたちの様子を写している。コメントにある通り、他のものが続いて海に飛び込んでいるのだからきっとそう行動することが正解であるように皆が考えているため、誰一人として自分や周りの行動について深く考えていない状況にある。本書の社会的証明の原則通りである。
以上が 第4章「社会的証明―真実は私たちに―」 の考察になります。
社会的証明は判断材料として用いる際には非常に重要な指標の1つですが、社会的証明の値が真実の数字かどうかを見抜く必要はありそうです。
そしてもっと詳しく知りたいと思った方はぜひ本書を購入して読んでみてください!
このブログでは紹介できていない事例が沢山乗っていて、深く理解することができます。
次回は第5章「好意ー優しそうな顔をした泥棒」を考察していきます。
それではSee you next time!!



コメント